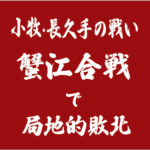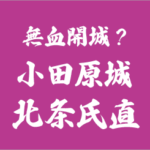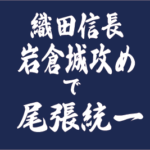豊臣秀吉の弟・豊臣秀長、温厚で誠実な人柄は、戦乱の世にあって兄・秀吉を支える”調整役”として多くの武将に信頼されました。
一方、淀殿(茶々)は、秀吉の側室として絶大な影響力を持ち、豊臣家の内政に深く関わった女性です。
史料は多く残されていませんが、二人は「秀吉を中心とした家族の中」で重要な関係にありました。
秀長と淀殿は表向きほとんど接点がないように見えますが、秀吉政権を安定させる上で、淀殿の感情と政治的思惑を最も理解していたのが秀長だったともいわれます。
その関係を、時代背景と人物像から探って見ましょう。
スポンサーリンク
淀殿(茶々)が豊臣家に入るまで
父は小谷城主の浅井長政と織田信長の妹・お市の方の間に三姉妹の長女(幼名:茶々・初・江)として誕生、正確な生年月日は不明であるが、『翁草』※1によると生年を永禄10年(1567年)とする説があります。
※1.翁草(おきなぐさ)とは、江戸時代に書かれた随筆で、前編・後編合わせて全200巻の書物で、京都町奉行所の与力を務めた神沢杜口が、曽祖父以来の蔵書や、先行文献、風聞や自身の見聞・体験を元にした、膨大な諸資料からの抜粋・抄写※2に神沢杜口自身の編著※3で、諸資料からの抄写に神沢杜口自身の批判や解説が加えられているものも多い。
諸資料の原典はすでに一般に広がっているものも多いが、近世後期及び京都の随筆として一級品の一つと評価されてます。
▲※.抄写(しょうしゃ)とは、文章とは文献の一部をそのまま書き写すことです。抜き書きや清書も含む場合があります。
※3.編著(へんちょ)とは、編集と著作。編集し、かつ著述したもの。
室町時代末期から寛政3年(1791年)までの約200年間の歴史的事実・人物、法制・裁判、文学・伝説、宗教・道徳、風俗・地理・経済などが書かれています。
人物の中でも織田信長や豊臣秀吉、歴代徳川将軍といった天下人・将軍の他、領主・大名・旗本から戦国武将・兵卒まで、武家が多く描かれています。他にも、皇室や公卿、僧侶や神職、学者・儒者・医者、芸能家・芸術家、茶人、碁打ちに棋士、農民・職人・商人まで、老若男女を問わず、あらゆる階層・地方の人々が登場しています。
神沢杜口は俳人だったため、俳人に関する記述は江戸中期の京都俳壇を優れた資料と評価されています。当時の人物や事件、世相を描いたものとして、多くの人が、この随筆の記載を引用しています。
天正元年(1573年)信長に包囲された小谷城から母に伴われて茶々おそらく6歳、妹2人(初・江)と共に脱出し、尾張清洲城で信長の弟・織田信包※4と言われてますが、実際は叔父である織田信次に養育されるが、茶々がおそらく15歳の時、天正10年(1582年)本能寺の変で信長が横死した。
※4.織田信包とは、織田信秀の四男(異説あり)で、織田信長の弟、通称三十郎。なお、一時長野工藤家に養子に入り伊勢国上野城17代当主となっているが、信長の命で養子縁組を解消して織田家に復してる。
兄・信長とは約9歳違い。
北近江小谷城で信長の義弟・浅井長政を滅亡させた時、その正室であった妹・お市とその娘たちである茶々・初・江を信包が保護したとされていますが、信長、信包、お市たちの叔父である織田信次※であることが明かになっています(『渓心院文』)。
※.織田信次とは、織田一族で信長の叔父、通称孫十郎、官位は右衛門尉。
兄の織田信秀(信長の父)に仕えていた。
尾張国の織田弾正忠家の当主・織田信定の子として誕生、美濃国岩村城の女城主・おつやの方と兄妹で兄の織田信秀に仕え、初めは深田城主になるが、天文21年8月15日兄・信秀の死後に清洲織田家の織田信友の重臣・坂井大膳らが、織田伊賀守の松葉城と、その並びにあった深田城を占領し、伊賀守と信次は人質として捕らえられた。
翌16日、甥の信長と兄・信光が駆けつけ、萱津の戦いが起こり坂井大膳側を敗走させ2人を解放、天文24年4月20日に清洲の信友が信長に滅ぼされ、兄・信光が守山城から那古野城へ移ると後任の守山城主となった。
信次が家臣を連れて龍泉寺の下の松川渡し(現・庄内川)で川狩りをしていたところ、一人の若者が馬に乗って通りかかった。
若者が馬から降りず挨拶もしないという無礼な態度だったため、信次の家臣・州賀才蔵は怒って弓で射殺した。
近づいてみると信長の弟・織田秀孝であるため信次は遺体をみるなり逃亡した。
守山城下は、弟の死に激怒した織田信勝(信長の弟で秀孝の兄)の軍により焼き払われた。
一方信長は「単騎での行動は軽率であり、秀孝にも咎めがある」とし、信次を追討しなかった。
信長の異母弟・織田信時が後任の守山城主を務めたが、重臣の角田新五の謀反に遭い自害したため放浪中の信次は信長に罪を許され再び守山城主に戻った。
天正元年(1573年)信長と対立した妹婿・浅井長政の小谷城が攻め落とされ、浅井氏が滅亡した時、お市の方と茶々・初・江の3姉妹は大叔父にあたる織田信次に預かられ守山城に滞在していたとされる(『渓心院文』)
天正2年(1574年)第三次長島一向一揆に参加するも戦死した。
お市の方は柴田勝家と再婚したが、天正11年(1583年)賤ヶ岳の戦いで豊臣秀吉と戦って敗れ、母と勝家は自害、三姉妹は城を出て秀吉の庇護を受ける。
茶々は約20歳の時、母と義父の仇である秀吉の側室になる。
天正11年(1583年)以降、やがて、秀吉の寵を受けることなり、天正17年(1589年)に茶々は懐妊する。
喜んだ秀吉は、弟・豊臣秀長を後見とし、細川忠興を補佐として山城淀城を改築し茶々に与えた。
スポンサーリンク
この後、淀殿と呼ばれる
この年5月27日に男児が誕生「棄」(のちの鶴松)が生まれるも同年19年8月5日(翌天正20年は、12月8日(グレゴリオ暦1593年1月10日)文禄元年)に病死してしまう。
豊臣秀長は天正19年(1591年)2月15日に郡山城で病死している。
天正20年(1592年)朝鮮に侵略の兵を出し、肥前名護屋城で諸軍を統率したが、淀殿も同地に随伴した。
この頃大阪城二の丸に移り「二の丸殿」と呼ばれていた淀殿は、陣中で懐妊し、文禄2年(1593年)8月3日に再び男児を産む、「捨」と名付けられ、のちの豊臣秀頼、慶長3年(1598年)8月秀吉没する。
翌年4年1月10日秀頼を擁して大阪城に移った。
スポンサーリンク
兄・秀吉の天下統一を陰で支えた温厚な智将
戦場での活躍と政務での手腕
豊臣秀長は、天下人・豊臣秀吉の実の弟として、戦場では勇敢に戦い、政務では冷静沈着に動いた人物でした。
派手な武勇伝こそ少ないながらも、二人の関係や豊臣家を支えた役割を読み解くことで、戦国時代の知られざる側面が見えてきます。
高い調整力
豊臣秀長が最も評価されているのは調整力です。
彼は秀吉と諸大名との間を取り持ち、豊臣政権を安定させたといわれます。
例えば、天正13年(1585年)の四国攻めでは、長曾我部元親との調和にあたり、領地を削減しつつも土佐国を安堵するなど条件を出して交渉を成立させるなど、また、徳川家康とも良好な関係を築き、様々な調整をしていたとされています。
さらに、秀長の死後、豊臣政権では石田三成・小西行長らの文治派※5と、武断派の対立が顕在化したことから、秀長が政権内部でバランスを取る役割を担っていたと考えられます。
※5.豊臣政権における文治派とは、石田三成、小西行長、大谷吉継など、政務を担う官僚系の武将たちを指します。
彼らは吏僚派(りりょうは)とも呼ばれ、武力中心の政治を行う武断派(加藤清正・福島正則など)と対立していました。
文治派は、法令や教化による政治を主義とし、主に中央集権的な政治を推進しました。
スポンサーリンク
軍事面での貢献
豊臣秀長は、軍事面でも豊臣秀吉の躍進を支えました。
例えば、秀吉が総司令官を務め、毛利輝元の勢力圏を攻略した「中国攻め」天正5年(1577年)〜天正10年(1582年)では、秀長は山陰道と但馬国平定の指摘を任されています。
また、「四国攻め」では病気の兄・秀吉の代わりに総大将を務め、わずか数ヶ月で長曾我部元親を降伏させるなど、迅速かつ的確な戦略を展開していました。
領国統治での手腕
豊臣秀長は、「四国攻め」を成功させた後、大和・紀伊・和泉などの約100石を領有し、大和郡山城を本拠としました。
秀長は検地の実施や盗賊の追補などを行い善政を敷いたと考えられています。
また、寺社勢力が強い地域でありながら、大きな禍根※6を残すこともなく統治を行ったことから、その巧みな手腕を伺い知ることができます。
※6.禍根(かこん)とは、わざわいの起こるおおもと・原因。「ーを除く」。▲
天正20年(1592年)秀吉は朝鮮に侵略の兵を出し、肥前名護屋城で諸軍を統率したが、淀殿も同地に随伴し、このころ大坂城二の丸に移「二の丸殿」と呼ばれていた淀殿は、陣中で懐妊し、文禄2年(1593年)8月3日に再び男児(秀頼)を出産した。
当初「拾」と名付けられたこの男児が秀頼で、淀殿は、翌年秀頼とともに伏見城西の丸に移り、「西の丸殿」あるいは「お袋さま」と呼ばれる。
当時の淀殿の権勢は、正室・杉原氏(高台院)※7を別格として側室の中では第一で、醍醐の花見の際、彼女に次ぐ位置にあった松丸殿(京極高吉女)との間で盃争いがあったことは有名である。
※7.杉原氏(高台院)とは、豊臣秀吉の正室・ねねのこと。
慶長3年(1598年)8月、秀吉が没すると、その遺命により、翌4年正月10日秀頼を擁して大坂城に移った。
翌年の関ヶ原の戦で、淀殿に近い関係にあった石田三成らが滅び、徳川家康が覇権を握ったことから、豊臣家の地位は著しく低下し、同8年までは、全国に分布した豊臣家の蔵入地も名目的には保持されたが、家康が征夷大将軍に補任されると最終的に接収され、秀頼は摂津・河内・和泉三国を領する大名となった。
しかし、朝廷の官位では秀忠に次ぎ、諸国の大名にもなお影響力を持っていた。
淀殿は、徳川氏の勢力に屈服することを嫌い、徳川氏の付家老(つけがろう)的位置にあった片桐且元を退け、大野治長を重用した。
同19年には、方広寺大仏殿の鐘銘を口実に豊臣家に人質提出あるいは転封を強要した徳川氏と開戦した。
一時講和が成立するが、再び戦端が開かれ、元和元年(1615年)5月8日大坂城は落城、淀殿は秀頼とともに城中で自害した。
「淀君」という呼称ははるか後世のもので、大坂城で絶大な権勢を振るったが、淀君の乱行などというのは、江戸時代の臆説である。
スポンサーリンク
まとめ
[参考文献]
『大日本史料』12の20 元和元年5月8日条、渡辺世祐『豊太閤の私的生活』、桑田忠親『淀君』(『人物叢書』七)
(山本 博文)※8
※8.山本博文さんの著作や関連研究において、示された3つの文献は豊臣政権末期から江戸時代にかけての歴史事象、特に大坂の陣や豊臣家の女性(淀君)に関する詳細な分析や史料解釈の根拠として言及されている可能性が高いと考えられます。
それぞれの文献の概要は以下の通りです。
『大日本史料』12の20 元和元年5月8日条:東京大学史料編纂所が編纂している包括的な日本史史料集の一部です。
第12編は江戸時代初期を扱っており、この「元和元年5月8日条」は、元和元年(1615年)5月8日の出来事に関する史料を集成したものです。
この日付は大坂夏の陣の落城当日にあたり、豊臣秀頼や淀君の最期、大坂城の陥落、徳川家康方の動向など、極めて重要な歴史的瞬間の詳細な記録が含まれていると考えられます。
渡辺世祐『豊太閤の私的生活』:
豊臣秀吉の公的な政治手腕だけでなく、その私生活や人間的な側面(例:女性関係、家族との関わり、趣味嗜好など)に焦点を当てた研究書です。
秀吉の人物像を多角的に捉える上で重要な文献であり、後世の歴史家(桑田忠親氏など)によって校訂されることもありました。
桑田忠親『淀君』(『人物叢書』七):
吉川弘文館の『人物叢書』シリーズの一冊で、豊臣秀吉の側室であり、秀頼の母である淀君(茶々)の生涯を扱った評伝です。
一般的に「悪女」というステレオタイプで見られがちな淀君の人物像に対し、史料に基づいた歴史的背景や彼女なりの立場からの行動を分析し、その悲劇的な生涯を描いています。
山本博文氏は、これらの文献を参照することで、豊臣家の滅亡に至る経緯や、関与した主要人物(秀吉、淀君、家康ら)の行動と背景について、実証的な歴史研究を行っていると考えられます。