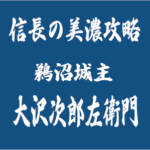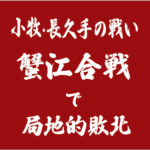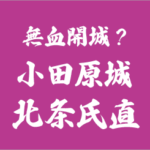豊臣秀次は、叔父である天下人の太閤秀吉の後継者として栄華を極めながらも、悲劇的な最期を迎えた人物です。
「なぜ秀次は殺されたのか?」「本当に悪人だったのか?」という疑問を持ちます。
秀吉の甥として次期太閤殿下になる予定でしたが、26歳か32歳?の若さで非業の死を遂げた豊臣秀次。
どうして秀次が謀反なんかと疑うのか?誰かが妬んで戯言が尾を引いて話を大きくしたのか?
「暴君」「色狂い」と悪評が伝えられますが、近年の研究ではまったく異なる人物像が見えてきました。
秀次の人生と悲劇の真相を分かりやすく解説します。
スポンサーリンク
秀次の切腹事件
従来の説では、文禄4年(1595年)に切腹事件が起き、理由としては、秀吉に嫡子・秀頼が生まれたから、秀次が邪魔になって秀吉が切腹を命じたというのが通説でした。
秀吉の後継者だった秀次が、謀反の疑いをかけられ、高野山で切腹し、その後、妻子も処刑された事件でしたが、近年では、秀吉の命令ではなく、自らの潔白を照明するために自ら命を絶ったのではないかという新設が有力になっています。
勿論、秀次が高野山で切腹したことは歴史的な事実です。
織田信長の一代記『信長公記』の著者・大田牛一による『太閤様軍記之内』には、秀次切腹の場面、そして、その介錯をおこなった篠辺淡路守について以下のように記されています。
“五番はん、関白秀次卿くわんはくひでつぎけう、御わきざし(脇指)はまさむね(正宗)にて、御かたななみ(浪)およぎ、さくかねみつ(作兼光)、ささべあわぢのかみ(篠辺淡路守)御かいしゃく(介錯)つかまつり候で、そののち、ぬし(主)も御わきざし国次をくたされ、はらをつかまり候、”
篠辺淡路守は、天下一の茶人・千利休の切腹を見届けた人物とされています。
月日が巡って、関白秀次の介錯役を務めた直後に殉死するという、なんとも壮絶な人生を送りました。
因みに『太閤様軍記之内』では、秀次及び殉死した者達の顔ぶれと共に、使用した刀剣類の名も書き残されています。
↓
一番:山本主殿には、脇差・国吉
二番:山田三十郎は、脇差・厚藤四郎
三番:不破万作は、 脇差・鎬藤四郎
四番:龍青西当は、 御剣・村雲
五番:秀次は: 脇差・正宗
六番:篠辺淡路守は、脇差・国次
いずれも名だたる名刀であり、刀剣類の「目利き」であったという秀次の教養や情勢をうかがい知ることができるでしょう。
何故かというと、豊臣宗家にとって最大の強みである「摂関家」という家格の象徴である「関白」に秀吉が切腹を命じるだろうか?
秀吉の命令は「切腹」ではなく「禁固刑」だった
『南行雑録』(東京大学史料編纂所写本)に残る、その法令の第一条には、
「一、召仕様者、侍十人此内坊主・①台所人共※1、下人・小者・下男共五人、都合拾五人タルヘシ、此外小者一切不レ可レ有レ之、然者、②ホツタイ黒衣之上ハ、上下共刀・脇差不レ可レ帯之事、」と記されています。
※1.台所人共とは、料理人のこと。
これを現代後に訳せば
「一、召し使うことのできる者は、侍十人[この内に坊主・台所人を含む]、下人・小物・下男五人を加え、十五人とする。
この他に小者を召し仕うことは一切禁止する。ただし、出家の身となり黒い袈裟を着けてる以上は、身分の上下にかかわらず、刀・脇指を携帯してはならない。」
ということに訳せます。
豊臣秀次とは
秀次は叔父さんである豊臣秀吉の姉(同父母)智の長男、秀次の父は尾張国海東郡乙之村の住人だった弥助という住人と結婚、永禄11年(1568年)に秀次(治兵衛)同12年に秀勝(小吉:淀の妹・江と結婚してたが病死)、天正7年(1679年)に秀保(辰千代:叔父の秀長の養子となる)を産んだ。
幼少時、戦国大名・浅井長政の家臣・宮部継潤※が秀吉の調略に応じる際に人質となり、そのまま養子となって、初名は吉継、通称を次兵衛尉とし、宮部吉継と名乗った。
※.宮部継潤(みやべけいじゅん)とは、近江国宮部城主、のち但馬国豊岡城主、因幡国鳥取城主。近江国坂田郡醒井の在地領主・土肥真舜の子として生まれ、天文5年位比叡山で行栄坊に師事し善祥坊と称した。比叡山を下り近江国浅井郡宮部村の湯次神社の社僧・宮部清潤の元に身を寄せ継潤と称し、その後、浅井長政の重臣になって織田信長と戦い羽柴秀吉と対峙したが秀吉の調略に応じた。
次いで畿内の有力勢力だった三好一族の三好康長の養嗣子となり、今度は名を信吉と改めて通称孫七郎とし、三好信吉と名乗って三好家の名跡を継いだ。
天正11年(1583年)頃に信吉が残り三好家の家臣団を率いる立場となり河内北山二万石の大名になり、百姓の倅が名門三好家を津田ということで父・弥助も三好姓を名乗り三好武蔵守良房と名乗りを改めた。
天正13年(1585年)、秀吉が紀伊雑賀征伐に出陣、その時に信吉(秀次)は叔父である豊臣秀長と共に副将を任され、先の小牧・長久手の戦いで見苦しい失態を挽回したく戦った。
太田城攻囲にも参加、続く同年6月に四国征伐では、秀吉が病気で出陣できず叔父・秀長が総大将となり、信吉(秀次)は副将となって出陣し、鳴門海峡を経て阿波国土佐泊に上陸し、黒田孝高、宇喜多秀家ら備前・播磨勢と合流、比江山親興の籠る岩倉城せめて楽城させた。
同年7月頃、秀吉の関白就任に前後して、その偏諱を受けて秀次と改名し、羽柴秀次を名乗る。
秀吉の第一子・鶴松が没して世継ぎがいなくなったことから、改めて秀吉の養嗣子とされ、文禄の役の開始前に関白の職を譲られ家督を相続した。
ところが、その後に秀吉に嫡子・秀頼が誕生して秀次は強制的に高野山に出家、そして蟄居となり切腹、秀次の首は三条河原で晒し首とされ、その際に眷族※2も尽く処刑された。
※2.眷族(けんぞく)とは、家族、親族などの血縁関係にある人々を指し、自分に従う家来や部下、または仏や神仕える存在を意味する場合もあります。
秀長が生きていれば秀次の切腹はなかったと思う。
なぜ秀吉が秀次を高野山に追放したのか?
文禄4年(1595年)7月15日、豊臣秀次は養父・豊臣秀吉に高野山に行くよう命じられ自ら潔白を証明するため自害して果てたのではないか?
秀吉が切腹を命じたなら事実なのか?豊臣家は成人男子が数少ないのに、なぜ切腹をいいつけたか?
まずは、どうして秀次が謀反を起こすだろか?
文禄4年(1595年)6月末に突然、秀次に謀反の疑いが持ち上がった。
秀次切腹事件を最初に描いた大田牛一『太閤さま軍記のうち』では、これを「鷹狩りと号して、山の谷、峰、綱りの中にて、よりより御謀反談合とあい聞こえ候」と描写している。
秀次を中心とする反秀吉一派※3が、鷹狩りを口実にして、山中で落ち合って謀議※4を重ねているという噂があったというものだが、これは当時の人々にとっても雲をつかむような話であり、俄に信じがたいものであった。
※3.反秀吉一派とは、真意の程はありませんでした、これは江戸時代に以降に作られた軍記物などによる汚名である可能性が高い、結論として、「反秀吉一派」は存在せず、秀次事件は秀吉の専横や後継者問題といった豊臣家内部の複雑な事情によって引き起こされた可能性が高いと考えられます。
豊臣秀頼の誕生と後継者問題: 秀吉に実子秀頼(拾)が誕生したことで、秀次が邪魔になったという「秀頼溺愛説」が最も有力な説の一つです。
石田三成ら奉行衆との対立: 秀次と、石田三成ら秀吉側近の文治派との間に政治的な対立があったとする説もありますが、これを裏付ける確かな史料は少ないと言われています。
秀吉の老いと疑心暗鬼: 晩年の秀吉が老齢による狂気や疑心暗鬼に陥り、後継者争いを恐れて無実の秀次を切腹に追い込んだとする説もあります。
秀次が実際に武力的な謀反を計画したり、大規模な反秀吉派閥を形成したりしたという具体的な証拠はないとされています。
むしろ、秀吉の意向を受けた周囲の動きによって追い詰められ、自身の潔白を証明するためにあえて切腹を選んだという見解も提示されています。
※4.謀議(ぼうぎ)とは、秘密の計画や相談を意味し、特に犯罪や陰謀を企てる際の相談を指します。
同年7月3日に、秀吉の命令により、石田三成ら4名(増田長盛・前田玄以・長束正家)の五奉行のうち4名が、秀次の謀反につて訊問(事情聴取や取り調べ)を行った
通説では、石田三成が秀吉に讒言して秀次を死に追いやったとされていますが、近年の研究では、三成はむしろ秀次を擁護しようとした可能性や、秀吉が切腹を命じたわけでもないとする説が出て来ています。
と事件の背景には様々な要因があったと考えられます。
結果的に秀次は、悲運な武将で真面目で自ら潔白を証明しようとして自ら高野山で腹を切って終わらせた。
秀吉にとっては、面子を保たなければならないので関係者全員を死に追いやったと僕は思います。
『おもひきや 雲ゐの秋のそらならて 竹あむ窓の月を見んとは』
この句は、豊臣秀次が最盛期に抱いた「まさか関白として秀吉の栄華を継ぐことになろうとは夢にも思わなかった」という無念さを表しています。
 ▲白い裃を身に着けて俯いた姿で座っている豊臣秀次
▲白い裃を身に着けて俯いた姿で座っている豊臣秀次
本武将浮世絵の中央にて、白い裃(かみしも)を身に付けて俯いた姿で座っている人物は、「豊臣秀吉」の跡を継ぎ、豊臣氏2代関白となった武将「豊臣秀次」(とよとみひでつぐ)。
また、明治時代に月岡芳年が描いた浮世絵『月百姿』の作品名としても知られ、秀次が切腹を命じらた状況を背景に、美しい秋の月が竹の格子越しに見えるという、作者の無念感が込められています。
句の意味と背景
「おもひきや」とは、「思っただろうか、いや、まさか」という意味の反語表現です。
「雲ゐの秋のそらならて」とは、「雲のない澄みきった秋の空」のことで、秀次が関白として栄華を極めていた頃の輝かしい日々を象徴しています。
「竹あむ窓の月を見んとは」とは「竹の格子が組まれた窓から月を見るような、みすぼらしい身になる」という意味です。
浮世絵『月百姿』とは、作者:月岡芳年、時代:明治22年、題名:『月百姿 おもひきや雲ゐの秋のそらならて 竹あむ窓の月を見んとは 秀次』。