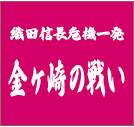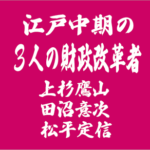兄・秀吉と二人三脚で天下統一に貢献した豊臣秀長。
豊臣秀長は、名古屋市中村区で生まれ、通説では幼名を小竹(こちく)という渾名でした(確認できる文章はないですが)。
『太閤素上記』には「是ハアダ名也」と書かれており、その説に従えば小竹は渾名※1で幼名は別に存在していたことになり、なんていう名前だったか?知りたいですね。
※1.渾名(あだな)とは、軽蔑または親愛の意図で、本名の他に、その人の特徴をとらえてつける名前。
スポンサーリンク
その小竹が、その後、小一郎と改称し実家で毎日百姓をして兄・藤吉郎を除いて日夜家族皆で働いて過ごしていた。
小一郎は土豪の娘・直(なお:仮名:永野芽都さんが演じている娘)と喧嘩しながらも思い思われの仲だったが、ある日兄・藤吉郎が帰還しお館様・織田信長に仕官した事を伝え、小一郎を無理矢理連れていき自分の家来にした。
その後、織田氏に仕官し、名前を木下小一郎長秀と名乗った。
秀吉が木下姓から羽柴姓に改名したのは、天正元年(1573年)以降であるが、秀長が発給した文章で羽柴を使用した初見は、天正3年(1575年)11月11日付けの発給文章からであり、羽柴小一郎長秀と署名しています。
天正元年(1573年)の主な出来事といえば、元亀3年(1573年3月5日)に上杉謙信が富山城の戦いに勝利し越中を平定、4月4日織田信長が二条御所に籠城した足利義昭を攻撃、4月12日の武田信玄が死去、7月18日は室町幕府滅亡、7月28日に元号が元亀から天正になった、天正元年(1573年8月20日)朝倉景鏡ら一族に裏切られ朝倉義景が自刃した、9月1日に浅井家の本拠・小谷城が落城した。
天正12年(1584年)6月8日から9月12日までの間に長秀から秀長に改名しています。
スポンサーリンク
金ヶ崎の戦いで殿を務めた羽柴兄弟
金ヶ崎の戦いとは、どういう戦いだったかというと、永禄13年4月20日(1570年5月24日)織田信長・徳川家康連合軍が3万の軍を率いて朝倉義景を討つため京を出陣した。
その他、池田勝正・松永久秀・近畿の武将、公家・日野輝資・飛び鳥井雅敦も従軍、出陣中の4月23日(1570年5月27日)に元号が元亀と改元された。
当初は織田・徳川連合軍が優勢に合戦を進めていたが、信長の妹・お市の方の夫・浅井長政の裏切りに遭い、挟撃の危機に陥った戦いで、信長が身の危険を感じて撤退した戦いです。
撤退に当たって、その殿(しんがり)を自ら藤吉郎が名乗りあげたとわれるが、『武家運箋』などのよると、殿軍には藤吉郎より地位が高い摂津守護の池田勝正や明智光秀がいたため、藤吉郎が殿軍の大将を務めたという説には疑問が残るが、結果的には藤吉郎が殿を努めることになった。
殿は危険な任務だが、弟・長秀はその中でも最も危険な一番隊長として金ヶ崎城に立て籠り、追撃してくる新倉軍と戦った。
命を懸けてお館様を救うと同時に、兄・藤吉郎の評価を上げることに貢献して戦った。
そして3年後、信長は裏切った義弟・浅井長政を滅亡に追い込み、この戦いで藤吉郎は小谷城攻めを任され、長秀は藤吉郎軍の先陣を切って夜襲をかけるなど武功を挙げた。
スポンサーリンク
長浜城の城代になって実務を発揮
秀吉は浅井滅亡の功績として旧浅井領の北近江約十二万石を信長から与えられ、新たな居城とし長浜城を築城した。
このように羽柴小一郎長秀は、数々の戦いで兄・羽柴秀吉を助け、弟・長秀は秀吉にとってなくてはならない存在となっていた。
それは合戦の場面だけではなかった。
長秀は、その城代を務め内政や実務も担っていった、長秀の下にも家臣が集まるようになってきて、その中に藤堂高虎※2がいて長秀(秀長)が亡くなるまで仕えた。
※2.藤堂高虎とは、伊予今治藩主、後に伊勢津藩の初代藩主になる。津藩藤堂家(藤堂家宗家)初代。藤堂高虎は黒田孝高(黒田官兵衛)、加藤清正と並び、「築城三名人」の一人。
スポンサリンク
中国攻めで活躍
信長は畿内を平定すると、次は中国攻めにとりかかり、その総大将を羽柴秀吉を任命した。
秀吉は山陽側を攻め、弟・長秀には但馬から山陰地方の攻略を任せ、長秀は「天空の城」として有名な竹田城を攻め落とすなど3年かかりで但馬地方を平定した。
 ▲天空の城
▲天空の城
この功績で長秀は但馬七郡約十万石を与えられています。
そして、天正10年(1582年)秀吉は備中高松城を水攻めで包囲し、弟・長秀も馳せ参上して合流した。
ここで長秀は、水攻めのための堤の設計や工事内容の検討、建設作業員の手当など事務的な調整を全て取り仕切ったという。
実務面でも秀吉を補佐していたのである。
スポンサーリンク
本能寺の変勃発
毛利攻めの最中、天正10年(1582年)織田信長は明智光秀によるが本能寺滞在中に襲撃を受け自刃した。
秀吉は本能寺の変を知り毛利軍と和睦「中国大返し」を敢行、長秀はまたしても殿を務めた。
幸い毛利軍の追撃はなかったが、天王山となった山崎の戦いで今度は先陣を務めるという奮闘だった。
その後も、天正11年(1583年)の「賤ヶ岳の戦い」の後、従五位下美濃守に任官され、播磨・但馬を拝領して姫路城主になった。
お館様から頂いた羽柴長秀は主・織田信長が亡くなったので、天正12年(1584年)に羽柴秀長に改名し、その後亡くなるまで秀長で通した。
天正12年(1584年)「小牧・長久手の戦い」など、天下取りのステップとなった。
※.上記の小牧。長久手の戦いをクリックして頂くと詳しい記事が載っています。興味ある方は読んでください。
スポンサーリンク
紀州攻めと長曾我部攻め
秀吉が紀州を攻めしたのは、まず天下統一の過程で、紀州の雑賀衆や根来衆などの勢力、特に根来寺を中心とする勢力が、秀吉の権威に挑戦していたためです。
根来寺は織田信長も攻めきれなかった寺院であり、秀吉にとって無視できない存在だったのでした。
また、根来寺が和泉を襲撃するなど、秀吉の勢力範囲に脅威を与える行動を起こしたことも、紀州征伐の決定的な理由となりました。
天正13年(1585年)秀長の紀州攻めの功績で、紀伊・和泉へ加増移封されて和歌山城主となり、さらに同年の四国攻めでは、病気の秀吉の代理として出陣し、苦戦しながらも長曾我部元親を降伏させた、この功から大和を加増され大和郡山城主となった。
天正14年(1586年)年頃から体調を崩すようになったが、同年に上洛した大友宗麟※3に秀吉は、「私的では千利休に、公的では宰相※4(秀長のこと)に任せている」と述べるほど欠かせない存在であった。
※3.大友宗麟とは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名、またキリシタン大名。大友氏の21代当主。宗麟とは法号、大友義鎮で洗礼名は、ドン・フランシスコ。最後の王と称された。
※5.宰相(さいしょう)とは、総理大臣のこと。首相。
翌年の九州攻めに日向方面の総大将として参加し、功績で従二位権大納言に叙任された(徳川家康との同時叙任)秀長だったが、天正18年(1590年)頃から病気が悪化して、小田原攻めには参加できなかったのでしなかった。
天正19年(1591年)に郡山城で病死し、享年51歳してしまった。
兄・秀吉と同じく子供に恵まれず実子は悉く(ことごとく)天折※5し、甥(長女・ともの子、秀次の弟)を養子としていたが4年後の文禄4年(1595年)に病死しお家断絶していないます。
※5.悉く天折とは、「すべてて若死にした」という意味です。若年で亡くなった、または、若年で死亡したという状況を指します。
スポンサーリンク
秀長の死後秀吉の暴走
秀長の死後の出来事をみると逆に弟・秀長の偉大さがよくわかります。
秀吉は、同年に千利休に切腹を命じ、翌文禄元年(1592年)に朝鮮出兵を開始、文禄4年(1595年)には、後継者だった豊臣秀次を切腹させた。
これらの出来事は有力大名や秀吉子飼いの武将たちに動揺や苦難を与え、豊臣政権を弱体化させる招いた。
秀長の死後の秀吉には、心から信頼でき、心から秀吉にブレーキをかける真のNo.2はいなかったという事ですね。