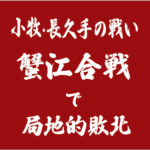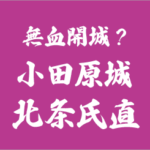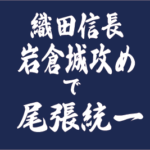豊臣秀長が長生きていたら天下を左右した参謀の可能性があるかもしれない?徳川幕府もなかったかもしれない?
小一郎(豊臣秀長)は、天下人・豊臣秀吉の異母弟として知られています(僕は父も母も同じだと思っていますが証拠がない異母弟も同様です)。
感情の起伏が激しい独断的な判断を下す兄を支え、常に柔和で理想的な弟は家臣たちからは「殿下(秀吉)を諫められる唯一の人」として家臣から信頼を集め、その温厚な人柄と的確な判断力で、兄・秀吉の天下統一を支えた弟の存在。
一方、浅井茶々(淀殿)は、浅井長政と母・お市の方の間に生まれた娘、叔父・信長との戦いで小谷城から母に伴われ妹2人と共に脱出し、守山城の母と信長の叔父・織田信次の保護下で暮らしていたが、天正10年(1582年)本能寺の変で明智光秀の謀反によって横死してしまう。
その上、長男・織田信忠と岩村城主だった幼名・御坊丸(織田勝長)※1▲も本能寺の変で自害、その後、信長の3男・神戸(織田)信孝は織田家家臣・柴田勝家との関係を強化するためお市の方を柴田勝家に輿入れさせた。
▲※1.織田勝長(御坊丸)とは、織田信長の四男か五男として生まれたが、岩村城主・遠山景任とおつやの方の間に子がなく養嗣子ととして美濃の岩村城に行き、幼くして武田家の人質となって甲斐で元服しており、武田家の戦略・戦術等を記した軍学書である甲陽軍鑑では、織田勝長(おだかつなが)と標記されています。
▲
母が再婚し義父となった・柴田勝家は秀吉と対立しており、天正11年(1583年)織田家の跡目を争って「賤ヶ岳の戦い」で敗北、居城越前北ノ庄城に逃げ込みお市の方と共に自害。
もし秀長が生きていたら
もし、秀長が天正19年(1591年)に亡くなっていなかったら豊臣家の運命はどういうふうに変わっていただろうか?
徳川家康との覇権争いは起きただろうか?
江戸幕府は出来ただろうか?
豊臣政権の後継問題
秀吉の晩年は、秀頼が幼いまま家督を継ぐことになり、石田三成と徳川家康を含む諸大名が力関係を巡って争う状態になった。
もし秀長が長生きしていれば、こうした後継問題の混乱を上手く調整出来たかもしれない。
豊臣政権は織田政権を継承して全国統一を目指していたが、信長も死去し豊臣政権ができ大名同士の対立や外征(朝鮮出兵)による負担など、国内外で課題が山積みだった。
徳川家康は、豊臣政権下では五大老の一角として大きな影響力を持っていましたが、もし秀長が生きていたら家康とのバランスをどうとっていただろうか?
関ヶ原の戦いはなかった可能性もあり徳川幕府も出来なかった可能性も?あったかも?
結局のところ、「秀長は亡くなっていたので、石田三成と徳川家康が関ヶ原で戦い豊臣秀頼の力が落ち」慶長19年(1614年)の大阪冬の陣、翌年の慶長20年(1615年)の大坂夏の陣で淀殿と秀頼が自害で幕が降りた。
スポンサーリンク
淀城はどこにあるか?
淀城は、現在の京都府京都市伏見区淀本町にあります。
住所で言えば、京都府京都市伏見区淀本町167です。
最寄駅は京阪本線「淀」駅、駅から歩いて5分程の所にあります。
▲ここに淀城の写真を入れる▲
茶々が淀殿と呼ばれる背景
茶々と妹2人、次女・初(常高院)・三女・江(崇源院)の三姉妹は、父・浅井長政が叔父・信長によって滅ぼされ、母・お市の方が柴田勝家と再婚した後、織田家や柴田家といった様々な庇護者の下を転々としていました。
最終的に、羽柴秀吉(豊臣秀吉)の庇護を受けることになります。
秀吉は、茶々を側室として迎え、淀城を与え、次女・初は、京極高次に嫁ぎ、夫と共に秀吉に仕え、三女・江は、秀吉の甥である豊臣秀勝に嫁いだ後、徳川家康の三男・徳川秀忠と再婚し、江戸幕府第2代将軍の御台所(正室)となった。
このように、茶々たち三姉妹は秀吉の庇護下に入ることで、それぞれ武家として重要な地位を築いていきます。
側室になった茶々は、やがて秀吉の寵を受け、天正17年(1589年)に懐妊する、喜んだ秀吉は、弟・豊臣秀長を後見人、細川忠興を補佐として山城淀城を改築し茶々の産所として整備し与えた。
この後、茶々は淀殿と呼ばれ、この年5月27日に男児を出産「棄」のちの鶴松と名付けられたが同年19年8月5日に病死してしまう。
スポンサーリンク
淀というところ
淀というところは「与渡津」(淀の港の意)と呼ばれ、古代には諸国からの貢納物や西日本から都に運ばれる海産物や塩の陸揚げを集積する商業地であった。
また、河内国・摂津国方面や大和国方面から山城国・京洛に入る要衛で、また、淀城は「宇治川(旧河道)と木津川(旧河道)の合流点に形成された島之内(現・京都市伏見区の京阪電気鉄道「淀」駅)の南西に位置します。
安土桃山時代、豊臣秀吉が側室・茶々の産所として築かせた淀城(旧淀城)は桂川と宇治川(旧河道)の合流点に挟まれた納所(現在の位置より北へ約500mの所にあった)。
こちらは、鶴松の死後に捨丸が誕生後、秀吉の養子となっていた豊臣秀次が謀反の疑いをかけられた際、城主であった木村重茲の連座と共に廃城となった。
豊臣家滅亡後、徳川幕府は西国防衛のためにこの地を重視して、元和9年(1623年)諸代大名の永井尚政が淀城の築城を命じられ石垣や堀を備えた堅固な城で伏見城・二条城と並ぶ京都防衛の要として機能していきます。
のちに稲葉家・永井家・松平家などが城主となり、幕末まで存続、淀川舟運の管理拠点でもあり、「水城」としての役割も果たしました。
淀殿の出産と豊臣秀長の死
淀殿が秀吉の第2子(豊臣秀頼)を懐妊したのは、文禄元年(1592年)の終わりの頃と推測されます。
秀頼は、文禄2年(1593年)8月3日(1593年8月29日)に大阪城で誕生しているため、その約9ヶ月前頃の時期に懐妊したと思われます。
第1子「棄」(鶴松)は、天正17年(1589年)5月27日に出産したが、天正19年(1591年)に天逝しています。
スポンサーリンク
秀長の死
天正17年1月1日(1589年)、大阪城にて諸大名と共に、秀吉に新年祝賀の太刀進上を行う(『後編旧記雑録』)、この後、秀長が大阪城を訪れたという記録はない。
同年3月、茶々が懐妊したので産所とするため淀城の改修を担当。
秀長は、天正18年(1590年)1月頃から病が悪化し、小田原征伐には参加出来ず、留守居を務めたて4月に大和郡山城に戻って静養、7月に後北条氏の滅亡と秀吉の帰京の知らせを受け再び京都に戻っています。
10月頃に秀次が秀長の病気回復の祈願のため談山神社を訪れており(談山神社文書)、両者の関係も良かったと思われます。
また、10月19日には秀吉が大和郡山城へ行って弟・秀長を見舞っています。
11月になると死亡説が流れ始め、秀長の花押が据えられていた発給文書に黒印が押されるようになる。
12月に入っても死去の噂が収まることはなかった。
天正19年(1591年)1月22日、郡山城内で病死、享年52歳でした。
家督は養嗣子になっていた甥(姉・智の息子、秀次の弟)の秀保に継がせた。
郡山城には金子56,000余枚と銀子は2間四方の部屋に満杯になる程の金銀が備蓄されていたという(多聞院日記)。