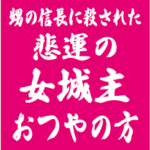どうして足利義昭は織田信長に上洛を頼んだか?
義昭は将軍職うを継ぐ正当な権利を持っていましたが、実力者の後ろ盾なければ京都にも入ることも将軍になることもできない状態だった。
当初、毛利氏や上杉謙信、武田信玄といった有力大名にも支援を求めたが、いずれも実現しませんでした。
その結果、信長への依頼が現実的な選択肢となった。
信長もその機会を利用して自身の権力拡大を図ったという、双方の利害が一致した結果だったと思います。
信長足利義昭を伴って京都へ凱旋
信長にとっても、義昭を将軍に擁立することは名目上「室町幕府の再興」という正当性を得る手段となり、信長は義昭を傀儡※1とすることで、自らの天下統一の足がかりしようと考えた。
※1.傀儡(かいらい)とは、あやつり人形。くぐつ。でく。
永禄11年(1568年)、信長が足利義昭を奉じて京都に入京することになった。

▲このイラストは永禄11年(1568年)に織田信長が足利義昭を奉じて京都に上洛した際の場面を描いています。この上洛により義昭は将軍職に就きましたが、信長の支配下に置かれる結果になります。(「AI生成」)
この歴史的瞬間は、信長の天下統一の第一歩であり、戦国の世を終わらせる布石となりました。
結果的に足利義昭は第15代将軍なったが、実際には信長の影響下で政治を行わざるを得ず、次第に両者の対立が深まっていき、最終的には義昭は信長に追放され、室町幕府は滅亡に至った。
織田信長の台頭
織田信長は、永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで今川義元を討ち取って以降、勢力を拡大していました。
永禄10年(1567年)には、美濃を攻略し、岐阜城を拠点として、自らを「天下布武」の旗印を揚げる戦国大名として名を高めていきます。
義昭が上洛を依頼した理由
信長への軍事力への期待
義昭は、信長が持つ軍事力と行動力を頼りにして、京都への進出を果たし将軍職を取り戻す事を目指したのは、義昭単独では、三好氏や松永久秀といった勢力に対抗する力がなかったため信長の助力が必要だった。
期待は見事的中した。
信長が足利義昭を奉じる意図は、義昭を利用して自身が天下統一する目録があった。
義昭は兄である13代将軍・足利義輝が暗殺された後、諸国を流浪していました。
信長の狙い
信長にとって、京都の制圧は単なる軍事的勝利ではなく、「天下布武」を掲げる上で不可欠なステップでした。
将軍・義昭を擁立することで、戦国大名たちに対する大義名分を得ることができたのです。
京都凱旋までの道のり
織田軍は、美濃国から京都へ進軍する際、」多くの困難を乗りこえました。
対抗勢力との戦いでは、近江国の六角氏が立ちはだかり、信長は巧みな戦術でこれを撃破し、道を切り開きました。
しかし、信長の進軍速度は驚異的で、敵に準備をさせる間を与えません、この迅速な行動が戦国大名としての真骨頂を示しています。
スポンサーリンク
基本的な部分で考えると、朝廷や幕府を牛耳ることによって権威付くのが第一の利点です。
京都入京の意義
信長が義昭を奉じて京都に凱旋したことは、単なる軍事的成功ではなく、それは、戦国時代という長きにわたる乱世の終焉を告げる象徴的な出来事でした。
足利義昭が将軍に就任したことで、一時的に室町幕府は再興されました。
しかし、実権は信長が握っており、将軍・義昭は名目上に過ぎません、信長が権力基盤を確立するために全国の大名に対し圧倒的な政治的優位を持つことになりました。
地方では威張れるでしょうが、地方で威張ったところで権力を行使できるのは朝廷や幕府内の話しです。
信長と将軍・義昭の関係
京都入京当初、信長と義昭の関係は協力でしたが、徐々に反信長になって反信長勢力と結びつくにつれて、両者の間に亀裂が生じていきます。
その結果、天正元年(1573年)信長は将軍・義昭を京都から追放し、室町幕府を事実上滅亡させ、この一連の流れが、信長の天下統一へと加速をもたらします。
スポンサーリンク
まとめ
織田信長が「足利義昭を奉じて京都に凱旋した出来事は、戦国時代を終わらせる布石でありました。
義昭という将軍を」利用しながらも、最終的にはその枠を超えた信長の戦略的手腕は、歴史の大きな転換点を作り出したのです。
このドラマチックな凱旋劇は、信長の「天下布武」の始まりとして後世に語り継がれています。