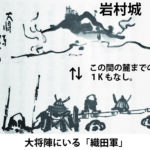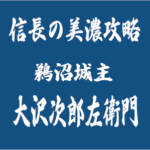秀吉の弟・豊臣秀長の正室はどんな人?
兄・秀吉の正室は、寧々(ねね)北政所で淀殿は側室(信長の姪、妹・お市の方の娘)だという事は皆さんご存知でしょう。
だけど弟・秀長の事はあまり知られていません。
何故かというと史料が少なくあまりよく分かりません。
だけど‘26年の大河ドラマの主人公となる豊臣秀長の正室や侍になる前の恋人について知りたいと思ってます。
当然ですが、恋人役が演じる直(なお)の事など名前も空想の作り話、正室役の吉岡里帆さんの慈雲院(ドラマでは慶(ちか)も名前は未です)は、そこそこ史料があるようですが、これもあまり残ってはいません。
さて、そこで‘26年の大河ドラマの主人公となる豊臣秀長の正室や侍になる前の恋人についてどう描かれるのか楽しみです。
兄・太閤秀吉の個性が強烈過ぎて史料が少なくなってしまっているのじゃないのかと思います。
また、弟・豊臣秀長は51歳という若さで病気で亡くなってしまったけど重要な人物だったと思われます。
そこで‘26年の大河ドラマの主人公となる豊臣秀長の正室や侍になる前の恋人について調べておきたいと思ってます。
スポンサーリンク
秀長の正室
豊臣秀長の生まれは、天文9年(1540年3月2日)(1540年4月8日)、尾張国愛知郡中村で生まれ、天正19年(1591年1月22日)(1591年2月15日)に郡山城内で病死、享年51歳です。
秀長の跡取りは男子がいなかったため、家督は養嗣子になっていた甥(長女・智※1の息子で豊臣秀次の弟)の秀保に継がせたが秀長の家系は四年後の文禄4年4月16日に17歳で死去したことにより断絶した。
※1.智(とも)とは、秀吉の姉で関白秀次の母親。大河ドラマでは宮澤エマさんが演じます。
豊臣秀吉の弟として知られる豊臣秀長、彼は戦国史上でも屈指の智将・名将として豊臣政権を影から支えた人物なのに正室についてもあまり史料がないです。
大河ドラマではどのように演出するのか見ものです。
はっきりしているのは、秀長の正室その女性は、慈雲院と云う女性です。
出自ははっきりしてないです。
天正13年(1585年)9月に、秀長の「女中」※2が郡山に来たとき『多聞院日記』※3にあり、これが秀長の正室、または側室であるとみられます。
※2.女中とは、秀長が郡山城に入城した際に伴い、秀長の女中が郡山にきたという記録はないと書いてあります。
天正13年(1585年)に大和国を加増されて奈良県大和郡山城に入城、これは筒井順慶が築城。
※3.『多聞院日記』とは、奈良・興福寺の塔頭・多聞院において、文明10年(1478年)〜元和4年(1618年)にかけて140年もの間、僧の英俊を始め、三代の筆者によって延々と書き継がれた日記です。
当時の近畿一円の記録が僧侶達の日記から分かる一級資料です。
文禄3年(1594年)3月に豊臣秀長が郡山城を訪れた際の『駒井日記』※4の記事に「ちうんいん様」「大かた様」とあり、これは秀長の正室を指すと考えられる。
※4.『駒井日記』とは、豊臣秀次の右執駒井中務少輔重勝の日記。《駒井中書日次記》《文禄日記》ともいう。
文禄2年(1593年)閏9月〜1595年4月の17巻のうち、巻ニ、巻六〜八、巻十七が現存し2冊より成る。
関白秀次及び太閤秀吉の動静を詳しく伝えると共に、関係文書を丹念に書き控えるなど、文禄期の政治史を知る上で第一級の史料です。
写本が内閣文庫、東京大学図書館にあり、自筆といわれる断筒が竜谷大学にあります。《改定史籍集覧》所収。執筆者:加藤益幹
文化19年(1809年)成立の『森家先代実録』にも、秀長の養女である智勝院の養母(秀長の正室)の法名として「智雲院」と記されている。
はい、智雲院と慈雲院は同じ人物です。
戦国時代から江戸時代初期にかけての女性で、豊臣秀長の正室でした。
天正19年(1591年1月22日)(1591年2月15日)に郡山城内で病死、享年51歳で亡くなった年、天正19年(1591年)5月7日、高野山奥之院の豊臣家墓所に逆修造立された石塔の刻銘は、大納言殿北方、すなわち大和大納言と称された権大納言秀長の正室の法名を慈雲院芳室紹慶とするとされています。
スポンサーリンク
秀長の後室・興俊尼
後室とは、身分のある人の未亡人のこと。
家の後ろの方にある部屋。と書いてあります。
興俊尼は、天文20年(1551年)-元和8年12月8日(1623年1月8日)戦国時代から江戸時代初期にかけての女性で、奈良興福院の住持。
豊臣秀長の側室とされるが、異説もあります。
俗名はお藤。法名は光秀尼ともいう。
父は大和の国人・秋篠伝左衛門、母も同じ大和の国人である鷹山頼円の娘。
スポンサーリンク
約90年後に書かれた奈良名所八重桜
『奈良名所八重桜』延宝6年(1678年)の作によると、興福院の元祖とされる興俊尼は元は法華寺の比丘尼で、ある日、法華寺を訪れた秀長に見そめらて城へと連れていかれ、一夜を過ごした後、寺に返されたという。
不犯の戒律を破った興俊尼※5は、母方の伯母※6で弘文院(興福院)の住職である心慶尼のもとに身を寄せ、懐妊の兆しが現ると、縁家の菊岡宗政の屋敷に移され、そこで娘・おきくを出産した。
※5.興俊尼(こうしゅんに)とは、天文20年(1551年)〜元和8年12月8年(1623年1月8日)、戦国時代から江戸初期にかけての女性で、奈良興福院の住持。
豊臣秀長の側室とされるが異説もあります。
俗名はお藤、法名は光秀尼ともいいます。
※6.伯母/叔母(おば)とは、父母の姉や妹、または父母の兄弟の妻。父母の姉には「伯母」、妹には「叔母」の字を用いる。叔父⇄伯父も同じ。
事情を知った秀長により郡山間城へ迎へられ、還俗した興俊尼はお藤と呼ばれた。
郡山城に入った時期は、娘・おきくが天正19年(1591年)1月に4・5歳とされることから天正15年(1587年)頃と見られます。
なお、『奈良名所八重桜』の記述に懐疑的な見方もあります。
興俊尼を秀長の側室とする話は真偽不明ともいわれています。
この場合、おきくの生母が誰であるかも不明となり、秀長の正室・智雲院の子である可能性も考えられています。
おきくは、天正19年(1591年)1月8日に秀長の養子・秀保(姉の子)と仮祝言を挙げ、その後本祝言を挙げた。
おきくは後の大善院ともみられ、大善院は文禄3年(1594年9月)、または文禄4年(1595年2月)に秀長の兄・秀吉の養女として毛利秀元に嫁ぎ慶長14年(1609年)に死去します。
『毛利家乗』によると享年22歳でした。
スポンサーリンク
豊臣秀長を支えた女たち
歴史の表舞台にたつ者の影には、必ず支える人物の存在者がいます。
豊臣秀吉の弟・豊臣秀長(木下小一郎)、彼は、戦国史上でも屈指の知将・名将として豊臣政権を陰から支えたが、その正室については語られることはないし史料もない。
正室の名は、慈雲院といいます。
慈雲院は、秀長と共に豊臣政権安定に尽してきたが詳細な記録は少なく歴史の中で語られる史料もない。
慈雲院の生涯や彼女が果たした役割を探りながら、秀長の妻としての視点から豊臣政権を見ていきたい。
慈雲院の出自は詳細な記録がないからハッキリとしてません。
一般には、大和(奈良)の国主領主の娘、或いは重臣の家柄ではないかと家系が不明です。
いわれていることは、豊臣家の家臣の娘であった可能性が高い、秀長が奈良、大和を統治するようになった時期と関係が深い、信仰心が厚く、慈善活動にも熱心だった。
慈雲院の生涯や彼女が果たした役割は。
スポンサーリンク
秀長の統治を支えた内政のサポート
秀長は大和(奈良)・紀伊・和泉の100石を統治し豊臣政権の基盤を築いた。
その中で、慈雲院は秀長の正室として、領国経営に深く関与したと考えられます。
◇領民との交流を重視し領国統治の安定に貢献しました。
◇寺社との繋がりを強化し仏教勢力を味方につけました。
◇戦乱で被害を受けた地域の復興支援を行った可能性がみられます。
特に、奈良や大和の統治では、寺社勢力との関係が重要なため、慈雲院は信仰心が厚く寺院との繋がりを深める役割を果たしていたと推測されます。
スポンサーリンク
戦国武将の妻としての務め
戦国時代の正室には重要な役割がありました。
◇家臣団との調整役
◇養子・縁組の取りまとめ
◇城の留守を預かる「城代代理」
羽柴秀長は多くの戦いに出陣したため、その間、慈雲院は城主の代理として城を守る役割を果たしていた。
豊臣家では養子縁組が頻繁に行われたが、その調整に慈雲院も関与していた可能性が高いと言われています。