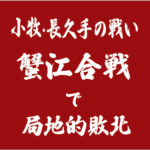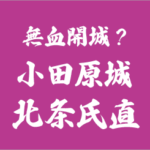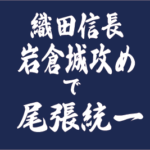世に名将あり、名参謀ありと呼ばれる人物は沢山いますが、名補佐役といわれる人物は極めて少ないと思います。
自分の器でトップになって会社を切もりしてやっていきたいと思う人は沢山いますが、誰にも邪魔されず思い通りに仕事をやりたい要するに社長業です。
一人では最初の内は上手くいきますが長い年月をやっていると色々な問題が出てきてきます。
その時にキツイ意見を言ってくれる番頭さん(補佐役)がいるといないとでは会社の運営が全然違うと思います。
そのためには信頼の置ける番頭さん・いわゆるNo2の信頼おける人を置くことです。
きつい意見を言ってくれる人物です。
自分では社長の器ではないNo2の器だと自覚してる人を探すことは容易ではないですが、探さなければなりませんので身内が一番ではないでしょうか。
そんな人物に戦国時代の秀長がいたと思います。
秀吉は運のいい人間だったと思います。
そんな激動の戦国時代、尾張の貧しい農民の出でありながら、野心家の兄・秀吉を天下人にし、自らも大和大納言と呼ばれるまでに上り詰めた男、それは秀吉の弟・秀長。
秀吉は周囲の人に恵まれいた秀長・黒田官兵衛・竹中半兵衛なしに秀吉は天下人になれなかったんじゃないでしょうか。
スポンサーリンク
統治能力を持った秀長
脆弱※1な豊臣家の体制を支え続け、また、抜群の調整力を持った豊臣秀長。
※1.脆弱(ぜいじゃく)とは、身体・組織・器物などがもろくて弱いこと。
この弟なくして兄・秀吉の天下はなかったと言っても過言ではない、戦国時代で最も優秀な兄弟といえます。
天正19年(1591年)1月22日は秀長の命日、兄・秀吉は、その7.8ヶ月後、慶長3年(1598年)9月18日、伏見城で亡くなっています。
家出した秀吉と15年ぶりの再会した小一郎
小一郎(秀長)は天文9年(1540年)尾張・中村で生まれ、兄・秀吉とは3歳違い(父親は木下弥右衛門ではなく再婚した竹阿弥と言ってますがはっきりしていませんが僕は同父と思っています。)
秀吉は10代半ばで家を飛び出していて、小一郎の幼少期のエピソードはないです。
大河ドラマで小一郎が親しく付き合ってた恋人(直)役に永野芽都さんが挑戦していますが、果たしてどこまでが真実かわかりませんが見ものです。
秀吉と小一郎が、再会するのは秀吉が寧々と結婚した後の永禄5年(1562年)のこと、家出してから約15年後小一郎が22歳の頃、それまで百姓として田畑を相手に暮らしていました。
結婚して子供が2・3人いてもおかしくない歳頃でした。
では、なんで秀吉は急に実家に帰って来たかというと、結婚の報告ともう一つ大事なことは秀吉は織田信長の下で足軽組頭を任されていたが、信頼できる部下はいなく家来は数10人いただけ。
元は百姓、何のコネもなかった。
そこで、真っ先に思いついたのが血縁者の小一郎でした。
小一郎は独身男兄弟は一人しかいなかったので、召し抱えにやって来ました。
家臣たちと打ち解けケアを請け負っていた
連れてこられた小一郎は木下軍に入る。
若い頃から温厚な性格で、秀吉の部下達とすぐ打ち解けていったが、段々大所帯になっていくと揉め事が起き、ちょっとした喧嘩や録(給料)などの些細な不満が積もって大爆発などという話は枚挙に暇※2がありませんでした。
※2.枚挙に暇がありませんとは、「一つ一つ数え上げている暇がないほど沢山ある」という意味の慣用句です。
個々人の感情のぶつかり合いは防げませんが、録(給料)に対する不満は雇う側が解決してやれる可能性があります。
戦国時代でも現代でも同じです。
秀吉は信長様から褒美を多く貰いたく戦功を挙げて自分の家臣に分与えなければなりません、遮二無二※3働かなければなりませんでした。
※3.遮二無二(しゃにむに)とは、他の事に気を取られずに、一つのことに全力を注ぐ様子を指す四字熟語です。他の言葉を気にせず、ひたすら一方向に進む様子を表す言葉です。
そのためには調略や工作などで留守にすることが多く、細かいところに目が行き届かないところも多々あったから、そういうところをフォローしたのが弟・小一郎の役目だった。
因みに、秀吉は姉妹の夫や義兄(妻・寧々の兄)なども家臣に加えていましたが、侍への転身は上手くいかず小一郎ほどの気の効く活躍はできませんでした。
信長美濃平定に走る
この頃、秀吉の主・織田信長が、美濃の斎藤龍興に起こした戦いで、永禄8年(1565年)〜永禄9年(1566年)に行われた合戦。
美濃(岐阜)は土岐氏が代々守護を務めていたが、斎藤道三が土岐頼芸(よりなり)を追い出し美濃国主となった。
信長の父、織田信秀と道三は何度も戦火を交えていたが、敗北を喫した織田家は、その後、平手政秀※4の働きにより信秀の嫡男・信長と道三の娘・帰蝶(濃姫)との縁組させることで和睦を成功させた。
※4.平手政秀とは、織田信秀・信長の二代に仕える、尾張国春日井郡にあった志賀城城主、織田信秀の重臣で外交面で活躍、信長が生まれると傅役となり次席家老を務めた。
斎藤親子は仲が悪く、弘治元年(1555年)に長良川で激突して道三は討ち取られる。
道三の死後、織田家と斎藤家との仲は険悪になっていく、信長な何度か美濃に侵攻したが義龍は手強く悉く追い払われてしまうが、永禄4年(1561年)5月11日に33歳で病死した。
跡を継いだ息子・龍興は、この時14歳だったが、直後に織田信長が美濃に侵攻し、森部の戦いで信長を迎え撃つが日比野清美※5・長井衛安と討ち取られ殺害。
※5.日比野清美とは、斎藤龍興の家臣で下野守を称し「斎藤六家老」の一人で美濃国結城の城主。
死後は同族で織田氏に仕える日比野六大夫の庇護下に入り、清美の妻・おつやの方※6(信長の年下の叔母で初婚)は織田家に戻った。
二人の間に嫡男あり下野守と名乗ったが実名は未、豊臣秀次事件に連座して自害、また、秀次に嫁いでいた娘・於和子も18歳の若さで処刑され、秀次との間の嫡男・豊臣仙千代も処刑された。
※6.おつやの方とは、織田信長の叔母で年下の叔母です。
初婚は日比野清美、次は信長の家臣、名前は未で死別、3度目が美濃国・岩村城の遠山景任、4度目が武田軍の武将・秋山虎繁。長良川で逆さ磔される。
更に、信長は墨俣という美濃浸出、この時に秀吉の一夜城の話が出てくる。
永禄6年(1563年)、美濃攻略のために本拠を清洲から小牧山に移し、北近江の浅井長政と同盟を結び斎藤龍興を牽制、この時、妹・お市を浅井長政の許に輿入れさせている。
永禄10年(1567年)、信長は斎藤家の本拠である稲葉山城を攻め陥落させ7寝かけて美濃を制定し岐阜と改める。
スポンサーリンク
金ヶ崎の撤退戦でも兄・秀吉を補佐して活躍
西美濃を手に入れた信長は、次に東美濃の有力な武士たちの工作を仕掛け、この調略に秀吉も少なからず功績を挙げ部下を2000人ほど抱えるようになります。
永禄10年(1567年)に斎藤氏の攻略に成功し、翌・永禄11年(1568年)に足利将軍・足利義昭を奉じて上洛が終わると、信長は京都での政務もするようになります。
京都で活躍する吏僚や警護役の武将を残している、その中に秀吉も秀長も当然入っていました。
※7.吏僚(りりょう)とは、官吏や役人を指す言葉で、特に役所の事務を処理する者を指します。
秀長は、この経験によって吏僚は主・秀吉を支え偉大すぎるNo2になっていきます。
金ヶ崎の戦いで殿を務めた羽柴兄弟は信長から、褒美として黄金20枚をもらっていますが、秀長の働きも大きく殿隊の中でも最も重要な最後尾を担当して、兄・秀吉から「信長様が出発してニ刻(今で言うと約4時間)だけ粘り、その後は粘らずさっと退いて、儂に追いつくように」と命じられて、その通りに働き見事役目を果たした。
記録はないが、秀長は兄・秀吉から褒美を何枚かもらった事でしょう。
秀吉横山城の城主になる
浅井長政への報復戦の「姉川の戦い」が終わると秀吉は浅井領から織田領になったばかりの横山城(長浜市)を任され、農民から足軽に出世して織田家の武将になって、初めての城主になったはいいが、秀吉は京都での仕事があり頻繁に京都と横山城を行き来できません。
まして、秀吉は浅井氏の攻略までの間にもいくつかの戦いがあり、信長に従ってあちこちへと出陣しています。
こうなると、城主である秀吉は城にいるのはほんの僅かな時間だけ、旧領を取り戻そうと浅井方の家臣たちの動きが多くなり、秀長と竹中半兵衛(重治)と共に浅井方と戦い城を守りました。
竹中半兵衛が秀吉の下に来たのは「姉川の戦い」の前だと言われています。
竹中半兵衛との出会い
元々竹中半兵衛は美濃の斎藤龍興に仕えていたが、当主、斎藤龍興に愛想が尽き。
半兵衛は竹中重元の子として、天文13年(1544年)大御堂(現大野町)で生まれたといわれ重虎とも称した。
永禄元年(1558年)父と共に岩手弾正を襲ってこれを追放し、岩手に移り住んだ。
幼少期より学を好み、もっぱら兵法の研究に励んだといい、成人して安藤伊賀守守就の娘を妻にし、父没後は斎藤龍興の下に属し、稲葉山城下に居館を置いたて住んだ。
永禄7年(1564年)2月、半兵衛は稲葉山城に人質となっていた弟・久作の病気見舞いと称して家臣十数名を率いて登城し、城外に待機していた安藤守就の軍勢とともに、主人・斎藤龍興を追放してしまった。
稲葉山城奪取の理由については、新年の饗宴の際、斎藤飛騨守が半兵衛を侮辱したためとも、龍興の家臣・日根野備中守と舅である安藤守就が争い、これを救うためとも、城主・龍興の愚行を戒めるためともいわれています。
この後、半年ほどで城を退去した半兵衛は、栗原山などに閑居していたといわれ、永禄10年(1567年)頃、織田信長に仕え、秀吉にこわれて与力の謀臣となった。
その後、秀吉と共に、永禄11年(1568年)9月、六角承禎の居城観音寺城奪取、箕作城攻撃、元亀元年(1570年)4月、越前朝倉義景の手筒山城、金ケ崎攻撃、同年6月には姉川の戦いに出陣した。
姉川の戦いに先立って浅井長政の重臣・鎌刃城主・堀次郎・樋口三郎兵衛を調略し、信長の近江攻略に功をあげた。
姉川合戦後、半兵衛は秀長と横山城を守り、数度の浅井・朝倉軍の襲撃を撃退した。
元亀元年(1572年)には、虎御前山在番を命じられた秀吉の先陣をつとめ、城の守りを固めて小谷城の浅井軍と対峙した。
浅井氏滅亡後も長浜に居城した秀吉に付き行動をともにした。
天正5年(1577年)、中国征伐を計画した信長は、秀吉を主将として派遣した。
半兵衛もこれに従い、秀吉が播磨に入ると、黒田官兵衛がその先導役を務め、その後、半兵衛・官兵衛の2人は、秀吉の下で行動を共にするようになり、播磨の上月城、福岡野城攻撃で軍功をあげた。
翌6年、信長の部将であった有岡城主・荒木村重が、信長に離反すると、官兵衛は有岡城へ向かい説得を行うが幽閉されてしまう。
官兵衛幽閉中、信長は謀反を疑うが、半兵衛は官兵衛を信じ、殺害の命のあった官兵衛の息子松寿丸(のちの黒田長政)を家臣の不破矢足邸に匿って養育した。
翌年、官兵衛は救出されるが、その時、半兵衛はすでにこの世を去っていた。
現在、不破矢足邸跡は五明稲荷社となっており、松寿丸が匿まわれた時に植えたといわれるイチョウの木が残っている。
天正6年(1578年)、中国毛利攻めの拠点であった三木城別所氏が毛利方へ寝返り、秀吉によって三木城攻めが行われた。
半兵衛は秀吉の補佐役として参戦、備前八幡山城主、明石影親の調略などに成功し、信長に銀子100両を与えられた。
しかし、出陣中、身体の不調を覚えた半兵衛は、一時京都で休養していたが、再度平井の本陣に帰り、天正7年(1579年)6月13日に没した。
秀吉は限りなくかなしみ劉備が孔明を失ったようだと号泣したという。
行年36歳、法号深龍水徹。