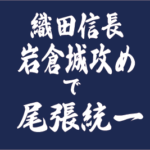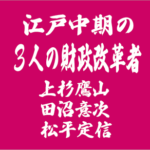こんにちは管理人の隆太郎です。
今日は江戸時代中期の米沢藩(現・山形県)の藩主・上杉鷹山の財政再建を中心とした藩政改革をみていきたいと思います。
そして日本は財政困難なのに野党の政治家たちのバラマキ。
何故ならもっと困窮して年金生活してる人たちもいるし、年収が低い低所得者もいるのに、なんで所得無制限でばら撒くのかな〜 票が欲しいだけだろうが年金者の数も多くなっている。
鷹山の改革は、質素倹約と産業振興を基盤にし、「為せば成る」の精神で藩を立て直したことで知られています。
この改革に影響受けた政治家・経営者は、財政再建、倹約、産業振興、教育重視、資本主義などの要素を学び、それぞれの時代に応用しました。
特にリーダーとしての模範を示す姿勢や、民のための政治の指導者に大きな与えた政治家・経営者たちの名前は?
スポンサーリンク
政治家たち
ジョン・F・ケネディ
ジョン・F・ケネディ(1917〜1963年)ケネディは上杉鷹山の「為せば成る」の精神に感銘を受け、彼を「世界で最も尊敬する日本人」と評しました。
鷹山の倹約と民主主義的な政治姿勢に共感し、自身の政治姿勢にも取り入れました。
ケネディの有名な言葉「国家があなたのために何をしてくれるのかではなく、あなたが国家のために何ができるのか問おう」鷹山の統治思想と通じるものがあります。
西郷隆盛
西郷高森は、(1828=1877年)鷹山の倹約精神や民政重視の政治手法を学び、明治政府の財政政策にも反映しました。
「敬天愛人」という彼の思想は、鷹山の「民を愛し、共に生きる」という統治哲学と通じるものがあります。
大久保利通
大久保利通(1830〜1878年)明治維新後の財政改革において、鷹山のような質素倹約と経済振興のバランスを考えた。
近代日本の産業振興策(殖産興業)は、鷹山の農業改革や産業育成と似た思想を持っています。
渋沢栄一
渋沢栄一(1840〜1931年)渋沢は、「道徳と経済の両立」を説いたが、これは鷹山の財政再建と民政改革の精神に通じろものがある。
鷹山が藩の産業を育成したように、渋沢も日本の企業育成を進めた。
松方正義
松方正義(1835〜1024年)明治政府の財政再建を担当し、鷹山のように倹約と経済政策を組み合わせた改革を行った。
緊縮財政を進める姿勢は、鷹山の藩政改革と似た部分がある。
吉田茂
吉田茂(1878〜1967年)戦後の日本復興に際し、鷹山の民本主義的な政策運営とリーダーシップを参考にしたとされる。
鷹山の「為政者が範を示す」という考え方を、日本の指導者として実践した。
スポンサーリンク
影響を受けた経営者たち
松下幸之助
松下幸之助(パナソニック創業者)鷹山の質素倹約と人材育成の重要性に学び、経営哲学に取り入れた。
稲盛和夫
稲盛和夫(京セラ創業者)「リーダーが範を示す」という鷹山の姿勢を尊敬し、経営に応用。
本田宗一郎
本田宗一郎(ホンダ創業者)「やればできる」という精神(為せば成る」を強調。
現在の代議士たち
現在の日本の政治家たち、 「非常にくだらないし小さい」野党は授業料・給食の無償化というバラマキに大きな声を上ていい気になって喋ってる。
年収の少ない低所得者の家庭には良い事です。
各家庭には、それぞれの年収がある、低所得の家庭もあれば、中流の家庭もある、もっと高所得者級の家庭もあります。
それを十把一絡げにして一律無償というのは、ただ政党の票が欲しいだけで大きな声を上て喋ってるだけだと思います。
生活の格差を考慮しなければ正常ではないと思う。
鷹山のように身を削ってやっている政治家が何人いますか?何が世直しと言えるのか。
上杉鷹山が上杉家に入った理由
あの上杉謙信は、生涯独り身で通し子供が居ませんでしたので、養子の一人・上杉景勝(謙信の姉の子)が跡を継いだのである。
上杉鷹山はもともと上杉家の出身ではなく、日向高鍋藩(現・宮崎県)の秋月家の生まれでした。
秋月家(鷹山の生家)で上杉家とは姻戚関係があったので、本名は、松平治憲で、上杉家に16歳で上杉家の養子として迎えら、明和4年(1767年)17歳で藩主に就任。
スポンサーリンク
なぜ米沢藩の財政は困窮したのか?
上杉鷹山の財政改革: 現代日本の政治家たちは学ぶべき教訓だと思います。
上杉家はもともと戦国時代に越後(現・新潟県)を支配していたが、関ヶ原の戦い(1600年)で敗北したため、米沢藩は30万石に減封された。
財政難の原因は、主に以下の4つが挙げられる。
(1) 領地の大幅な減少
上杉家は関ヶ原の戦いの後、120万石から30万石に減封された。
しかし、家臣団の規模(約5,000人)はそのまま維持したため、支出が収入を大きく上回った。
(2) 藩士の給料負担が大きすぎた
上杉家は家臣を大事にする方針だったが、30万石では全員の生活を支えるのが困難だった。
給料(知行)を削減できず、財政が苦しくなった。
(3) 借金の増加
米沢藩は度重なる飢饉(ききん)や災害の影響で財政が悪化し、借金を重ねた。
上杉家は格式を重んじる家柄で、武家の面子(めんつ)を保つために無理な出費を続けた。
その結果、藩の借金は20万両(現在の価値で約200億円)に膨れ上がった。
(4) 天候不順
飢饉18世紀の東北地方は冷害が多く、米の収穫が安定しなかった。
さらに、「天明の大飢饉(1782~1788年)」が発生し、多くの領民が餓死する事態に。
これにより藩の収入が激減し、ますます財政が悪化した。
スポンサーリンク
鷹山の藩政改革
上杉鷹山は、江戸時代中期の大名で、米沢藩(現・山形県)の藩主として藩政改革を行いました。
彼の改革は、藩の財政を立て直し、領民の生活を安定させることを目的としたもので、日本史上でも成功した改革の一つとして評価されています。
上杉鷹山の改革の概要
1. 改革の時代と背景
江戸時代中期(18世紀後半)藩の状況は最悪、米沢藩は財政難に苦しみ、莫大な借金を抱えていた(約20万両とも)藩財政の破綻寸前の状態で、藩士や領民の生活も困窮していた。
2. 上杉鷹山の改革内容
(1) 倹約政策
藩主自ら質素な生活を実践し、藩士にも倹約を徹底させ、藩の経費を大幅に削減し、無駄な支出を抑えた。
(2) 殖産興業(産業振興)
それには農業改革で新田開発や農具の改良を奨励し、農民の生産性向上を支援し、また、特産品の開発、米沢織(織物産業)や紅花(染料の原料)などを奨励し、藩の財政を支えた。
養蚕業の振興で絹織物の生産を推進し、米沢の経済基盤を強化していった。
(3) 教育の充実にも力を入れた。
藩校「興譲館(こうじょうかん)」を設立し、藩士や領民に学問を奨励させた。
実学を重視し、農業・商業・技術に関する教育を推進した。
(4) 人材登用
身分に関係なく有能な人材を登用し、能力主義の政策を推進した。
下級武士や商人階級からも優れた人材を採用し、藩政改革を実行した。
日本の国会議員も優秀な人材もいる、民間でもそれ以上の人材もいる、それらを使い分けるのがトップである、議員で何回当選してるから大臣にしなくちゃというのはアホのトップのやること。
(5) 財政再建
借金の返済計画を立て、財政の立て直しを図る。
増税ではなく産業の活性化によって収入を増やし、藩の財政を改善していった。
スポンサーリンク
改革の成果
米沢藩の財政は大幅に改善され、藩士や領民の生活も安定していった。
上杉鷹山の統治理念「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」は後世にも語り継がれる。
鷹山の改革は、日本国内だけでなく、後にアメリカのジョン・F・ケネディ大統領が「最も尊敬する日本の政治家」として彼の名を挙げたことでも有名な話です。
まとめ
上杉鷹山が米沢藩に入ったのは、上杉家に跡継ぎがいなかったため、縁戚関係のある秋月家から養子に迎えられたからです。
一方、米沢藩の財政が困窮したのは、関ヶ原の戦い後の減封、過剰な家臣団維持、度重なる飢饉と借金の増加が主な原因でした。
上杉鷹山の改革は、質素倹約と産業振興を組み合わせた持続可能な政策でした。
指導者自らが率先して模範を示すという姿勢は、現代のリーダーシップにも通じる重要な要素です。
財政破綻寸前だった米沢藩を立て直し、後世に名を残した彼の改革は、日本史上でも成功例として高く評価されています。
鷹山はこの厳しい状況の中で、財政改革を断行し、藩を立て直したのです。