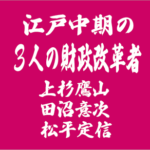嘉永6年(1853年)、アメリカの「ペリー」率いる艦隊が日本に開国求めて浦賀に来航したことを発端にして、徳川家による江戸幕府の統治体制が崩壊しました。
慶応3年(1867年)に江戸幕府15代将軍・徳川慶喜は政権を天皇に返上する「大政奉還」を行い、慶応4年/明治元年(1868年)に、天皇を中心とする中央集権国家を目指した明治政府が誕生した。
これにより、武家政治が廃止、天皇中心の体制が確立されました。
これにより、日本は封建制度から中央集権的な近代国家へと転換し明治時代が始まりました。
そんな折、明治4年(1871年)1月14日に尾張藩62万石の釣姫(30歳)が美濃国岩村藩の第8代藩主・松平乗命(乗政流大給松平家8代、官位は従五位下・能登守。維新後は子爵)にお輿入れしてきた。
父は尾張藩主12代・徳川斉荘、祖父は徳川将軍11代・徳川家斉、叔父に徳川将軍12代・徳川家慶、ビックなビックなお姫様を妻に迎え入れました。
明治政府は藩制度を廃止、全国を「県」に再編、そのため、岩村藩・松平乗命は廃され明治4年(1871年)8月29日の廃藩置県によって岩村県となり、県庁は旧藩庁(岩村城下、現・岐阜県恵那市岩村町)に置かれました。
旧岩村藩領(現・岐阜県恵那市・中津川市の一部などを所管、面積は小さく、周辺の苗木県・大垣県・高山県などと同様に岩村県は長く存続せず、同年11月には統合が進みました。
岩村県誕生
公式に「藩」という制度が存在したのは、明治2年(1869年)の版籍奉還から明治4年(1871年)の廃藩置県の2年間。
廃藩置県によって岩村藩(その他の藩も同様)は廃止され、松平乗命は藩主の地位を失った。
釣姫は廃藩置県前に亡くなったので、尾張藩・徳川斉荘の四女・釣姫、松平乗命の正室のまま生涯を終わっています。
明治政府が、それまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の「府」または「県」に一元化した行政改革です。
沖縄は明治12年(1879年)に琉球藩を廃して沖縄県を設置。
300弱の藩を廃止して、そのまま「国」の直轄の県とし、その後、県は統廃合された。
府・県知事は東京居住が強制された。
明治2年(1869年)、松平乗命は版籍奉還により岩村知藩事に任じられたが、明治4年(1871年)2月、東京府貫属に命じられ、7月には廃藩置県により知藩事を免官※1された。
※1.免官(めんかん)とは、官職を辞めさせること。
岩村県の廃止
廃藩置県から2ヶ月半後、府県統合令により県の大合併が実地され、岩村県は名古屋県に編入される(名古屋県は旧尾張藩領などを管轄していた県)。
名古屋県は愛知県に改称、その後、岐阜県との間で再編があって、旧岩村県地域は岐阜県移管される。
この再編で、現在の岐阜県恵那市・中津川市の一部として定着されました。
明治4年(1871年8月29日)岩村藩は→岩村県(県庁:岩村城下)、同年11月14日岩村県は→名古屋県に編入され、明治5年(4月18日に名古屋県改称されて愛知県)編入されていた岩村県は→岐阜県へ移管される。
スポンサーリンク
尾張藩の姫・釣姫お輿入れからご逝去
尾張藩・徳川斉荘の四女・釣姫のお輿入れは、明治維新の慌ただしさが残る明治4年1月13日、岩村藩がまだ、健在だった時期の出来事です。
名古屋を出発した釣姫のお輿入れ行列が下街道※2を通って美濃の岩村へゆっくりと進んで行きます。
※2.釣姫が通った下街道とは、名古屋〜高山陣屋(土岐市)〜岩村間。
名古屋を出発して→大曽根→勝川→坂下→内津→池田→高山(天領)→土岐(岩村領)→釜戸(大島家知領)→竹折→大井→岩村藩へ。
 ▲釣姫を乗せた駕籠(イメージ)
▲釣姫を乗せた駕籠(イメージ)
この時点では、まだ廃藩置県が発令されていないため、釣姫「藩主夫人」としての地位を保持したままお輿入れができました。
姫のお輿入れのため新調した漆塗りの駕籠に乗って「いざ「岩村藩」へ向かいましたが、漆によって「かぶれ」て発熱してしまいました。
到着間もなく御典医の手厚い看護も及ばず短期間で体調が悪化、わずか3ヶ月目に黄泉の国へ・・・旅たちました。
4月頃釣姫(30歳)で亡くなったと記録されています。<
今も岩村町の隆崇院の境内に(岩村駅の近くにあります)にお墓があります。
※.上記の釣姫をクリックして詳しい記事を読んでください。

 ▲尾張藩の釣姫が眠る墓(後ろに見えるのが岩村城です)
▲尾張藩の釣姫が眠る墓(後ろに見えるのが岩村城です)
その後、藩制度の廃止は明治4年7月14日の廃藩置県によって断行されました。
明治政府が全国の藩を廃止して、国が直接管轄する府・県に統一する改革で、これにより江戸時代以来の幕藩体制が終止符を打ち、近代的な中央集権国家が確立されました。