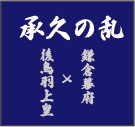大河ドラマ「鎌倉殿の13人」という番組を、ご覧になっている皆様江間次郎と江間小四郎は、同一人物なのか?
はたまた別人なのか?
知りたいですよね。
八重姫は確かに頼朝の件があって江間次郎に嫁いでいる。
子まで儲けている。
大河ドラマでは飛ばしているが、江間次郎との間に子は産まれた。
スポンサーリンク
父・祐親が嫁がせた江間次郎なる人物
平治の乱で源義朝・頼朝が敗れ、永暦元年(1160年)2月9日、頼朝は近江国で捕らえられ六波羅へ送られ、死刑を当然視されるが、平清盛の継母の池禅尼の嘆願などにより免れる。
それで伊豆蛭ヵ島に流罪となって、その時頼朝は13歳、当地の豪族武士・伊東祐親・北条時政親子の監視下に置かれる。
伊東祐親が京の大番役を終えて帰って来ると、娘・八重姫が子・千鶴丸を産んでいた。
びっくり仰天した祐親は、妻に問うとその相手が頼朝、激怒して、安元元年(1175年)、頼朝29歳の9月頃、伊東祐親が頼朝を殺害しようとした。
千鶴丸が3歳ということ、祐親が京から戻って来たのが3年後だから、京へ行ったのが1172年(承安2年)頃と推察します。
ということは頼朝が25・26歳に八重姫といい仲になったということですね。
そこで祐親は、娘・八重姫を江間(狩野川を挟んだ北条の里にある地)江間次郎に八重姫を嫁がせた。
 ▲この川はは現在の狩野川です。どちらが北条家か江間家か分かりません。
▲この川はは現在の狩野川です。どちらが北条家か江間家か分かりません。
確かな確証はないけどWikipediaによると、江間次郎は平安時代後期の武士。
伊豆国田方郡江馬庄(現・伊豆国市江間)の人物と考えられ、主に『曽我物語』にその名がみられると書いてあります。
江間次郎と伊東祐親は頼朝挙兵の時、平家方についたため源氏と戦ったが戦死、江間氏の所領は北条氏のなった。
『豆州志稿』にはこのように記されている
「頼朝は八重姫が嫁いだ江間次郎を殺害し、その子を義時に育てさせ、元服したのちには義時を烏帽子親として小次郎と名乗らせた」とある。
真名本『曽我物語』にはこのように書かれています
江馬(江間)次郎は、頼朝が挙兵した後、伊東祐清(祐親の子、八重姫の兄)と共々加賀国で討死し、その子は義時が教育して「江間小四郎」と名のらせたのだという。
また、江間次郎が討死したのは寿永2年(1183年)となっています。
流布本『曽我物語』には
八重の息子・江馬小次郎の死後、その跡は北条義時が、その名を引継いだと記されている。
いずれも語り伝えられてきた話なので、江間の地が北条氏の所領の前は江間次郎なる人物が支配してたのは確かなのかもしれない。
スポンサーリンク
その後新たに江間で義時の子を産む
第3代執権・北条泰時です。
当時の八重姫の年齢は分かりませんが、僕の推測では1160年頃の生まれと計算した。
※上記の年齢をクリックすると計算して出した、頼朝・政子・義時・八重姫のおおよその年齢がわかると思います。
北条義時は長寛元年(1163年)生まれですので、八重姫より3・4歳年下の計算になります。
長男ができた時、義時21歳ですから、八重姫は24・25歳だと思います。
北条義時が吾妻鏡に登場する時期は
治承4年(1180年)に源頼朝が挙兵して相模国進軍した8月20日、この時の名」北条四郎義時」としているが、翌1181年4月、義時は頼朝の寝所警護11名の一人に選ばれるが、この時の名は「江間四郎」と記されている。
この頃に江間の地を得たのかも。
以後、『吾妻鏡』では、義時のことを「江間」「北条小四郎」「江間四郎」「江間殿」「江間小四郎」「江間四郎殿」「江間小四郎殿」などと呼ぶようになってきた。
まだ、義時が12・13歳の頃は、江間は狩野川を挟んで北条の里の対岸にあった地、まだこの時は義時の所領ではなかった。
なので八重姫と結婚してはいないので、当時の江間次郎と結婚したのが事実として浮かび上がってきた。
頼朝の挙兵後、江間に嫁いだ八重姫の子を義時が育てたのが事実なのであれば、義時と八重姫の結婚があっても不思議な事ではないのかもしれない・・・
江馬 次郎(えま の じろう)は、平安時代後期の武士。
慶本『平家物語』『源平盛衰記』『源平闘諍録』『曽我物語』などの物語類にのみ登場し、同時代史料や『吾妻鏡』など後世の編纂史料には見えない。苗字を江間、江葉とするものもあるがいずれも「えま」と読む。
延慶本『平家物語』『源平盛衰記』では「エマノ小次郎」、『源平闘諍録』では「江葉の小次郎近末」、真名本『曽我物語』では「江馬次郎」、流布本『曽我物語』では「江間小四郎」と記される。