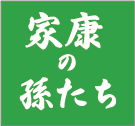この2人は豊臣政権下では五大老のメンバーでしたが、関ヶ原の戦い時では徳川家康は東軍の大将、毛利輝元は西軍総大将と東西に分かれた。
西軍のメイン実行はメンバーは、石田三成・大谷吉継となっています。
天下人だった豊臣秀吉が晩年、自分の死後に幼い息子・豊臣秀頼を支えて、豊臣政権を運営して行くための準備をした。
それが、「五大老・五奉行」というシステムである。

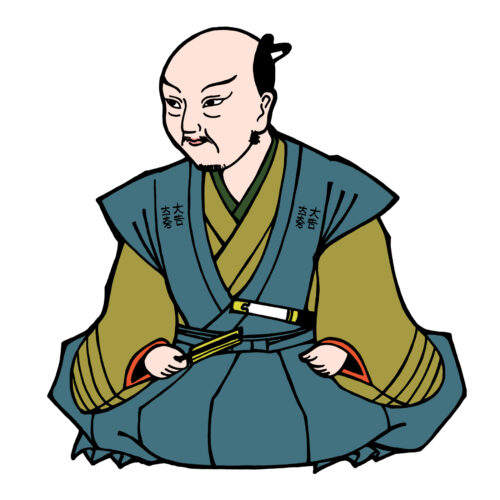
▲五大老の一人家康 ▲五奉行の一人三成
五大老のメンバーは、有力大名の「徳川家康・前田利家・毛利輝元・上杉景勝・宇喜多秀家」。
五奉行は有能な官僚で、「石田三成・増田長盛・中束正家・前田玄以・浅野長政」。
五大老と五奉行は役割分担しつつ、合議によって政務を取ることになっていた。
秀吉の死後に亀裂が起きる
生前秀吉は朝鮮出兵を行い、慶長3年(1598年)8月に没すると、朝鮮出兵は中止されるが、武断派※1だった加藤清正・黒田長政・藤堂高虎ら最前線で戦っていた諸将と、石田三成らの吏僚派※2との対立だった。
※1.武断派(ぶだんは)とは、武力を用いて政治を行おうする立場の人々。
※2.吏僚派(りりょうは)とは、役人。官史。つかさびと。
武断派は自分達の働きを三成らが正しく秀吉の耳に入れず、そのために秀吉から譴責※3を受けたとして激しく憎んだ。
※3.譴責(けんせき)とは、従業員から始末書を提出させて、厳重注意する懲戒処分をいいます。
毛利輝元の甘い本心が かいま見えた
毛利輝元は、石田三成と安国寺恵瓊らの後押しで、西軍の総大将に祭り上げられて大阪城から動かなかったように語られているが、果たしてそうだろうか?
事実は、輝元は大阪城の奉行らが「内府ちかひの条々」※4を発すると、広島から僅か2日という異例のスピードで大阪城入り、甥の毛利秀元も6万の大軍で大阪城に入るなど、極めて積極的あった。
※4.「内府ちかひの条々」とは、慶長5年(1600年)7月17日に大阪三奉行(増田長盛・長束正家・徳善院玄以)が出した、徳川家康に対する13ヶ条の弾劾状(一つ書きで記載)である。
慶長5年(1600年)7月、徳川家康は上杉景勝を討伐するため、少しずつ会津に迫っていた。しかし、大阪では石田三成を中心とする面々が「反 家康」を唱え、挙兵の準備を着々と進めていた。
そして、三成らは各地の大名に対して、家康を討伐するため「内府ちかひの条々」を発し挙兵を促している。
全ては、秀頼つまり豊臣公儀を存続させるためであった。
何が甘いかというと毛利輝元は、生前豊臣秀吉が「東国は家康、西国は輝元に任せる」と言っていたことから、毛利輝元には「自分は西国の統括者である」という意識が強く、この時も熊本の加藤清正に従うよう促している。
ただし、家康と正面から勝負するつもりはなく、むしろ輝元の関心は、戦いに乗じて四国方面など西国に毛利を領を拡大することにあった。
そんな輝元を、西軍は総大将に据えざるを得なかったのである。
結果的に西軍が負けて東軍が結果的に勝った。
家康の毛利輝元の処遇
西軍の総大将・毛利輝元はどうなったのでしょうか?
毛利氏安泰のため東軍と内応した吉川広家の尽力により、「安国寺恵瓊ら謀反人によってやむなく西軍の総大将に祭りあげられたのであれば責任はない」と徳川家康が解釈を示し、毛利輝元は、所領の安堵を約束して貰うことを条件に大阪城を去った。
しかし、すぐに毛利輝元が西軍総大将として数々の行ないをしていたことがわかると、家康は、所領安堵の密約を反故にし、毛利氏の領国である中国地方の安芸・周防・長門・石見・備後・備中・出雲・隠岐の8カ国120万5000石の全てを没収した。
一方、徳川家康は吉川広家に対しては、中国地方で1、2ヵ国を与える旨を伝えました。
これに一番驚いたのが、当の吉川広家です。
毛利氏安泰のために動いたことが、これではすべて水の泡で、かつ自身は主家を滅亡に追い込んだ張本人となってしまいます。
そこで吉川広家は、自らに与えられる所領をすべて毛利輝元に譲ることを徳川家康に直談判。
これにより、毛利輝元は、結果的に83万6,000石の減封となったものの、周防・長門の2ヵ国36万9,000国の領主として、毛利家を存続させることができたのです。
毛利氏は、ある意味、大勢力であったがゆえに、主要人物達の間で違う判断基準が生まれてしまいました。
「関ヶ原の戦いという一大決戦において、右往左往した大勢力・毛利氏の顛末は、喜劇的でさえある」とも言われています。