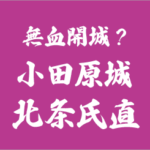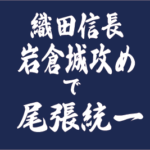幕府という名の付くのは、鎌倉幕府・足利幕府・徳川幕府の三つです。。
その幕府を開くには征夷大将軍という官職を天皇・朝廷から任命してもらわなくてはなれません。
なれれば武士の棟梁になることです。
この両者がうまくいけば世の中平和に過ごせます。
ところが、徳川家が征夷大将軍という役職を貰ったのが、慶長5年(1600年)に家康が関ヶ原の戦いを制し、慶長8年(1603年)に朝廷から征夷大将軍に任命さます。
僕個人としての意見は、何で?貰えたのか不思議と思っています。
スポンサーリンク
この「征夷大将軍」という役職は、古代、朝廷が、その権力に従おうとしない東北地方の蝦夷を武力で屈服するために生み出した“令街の官”※1です。
※1.令外の官とは、律令国家の令に規定のない新設された官職のこと。
つまり、もともと阿弖流為※2を中心とした東北地方の服属3※しない人々(蝦夷)を武力征伐する将軍という名目で設置されたのが「征夷大将軍」の始まりだったのです。
※2.阿弖流為(あてるい)とは、参考URLをご覧になってください。
上記の阿弖流為をクリックして頂くと参考URLにつながります。
※3.服属(ふくぞく)とは、部下となって)服従し従属すること。「大国に〜する」
そんな、
「征夷大将軍」は鎌倉幕府を開いた源頼朝以降、朝廷が公的に武家の棟梁としての地位を保障する役職となりました。
これをもって全大名に対する指摘権を正式に手に入れ、江戸幕府を開くことができました。
スポンサーサイト
江戸幕府と朝廷の関係
武家政権を担う者にとって天皇が認めた武家のリーダーというお墨付きは、支配の正当性を示すために必要なものなのです。
それがどうして徳川幕府と朝廷の関係が悪くなったのか?
徳川家康は、慶長8年(1603年)に朝廷から征夷大将軍に任命され、これをもって全大名に対する指摘権を正式に手に入れ江戸幕府を開くことができました。
江戸幕府は、禁中並公家諸法度というものを定め、歴史上初めて天皇家の行動に規制をかける。
実質的な力関係において朝廷の上に立ち、その圧倒的な支配力を強めて行ったのです。
力は徳川幕府が握っても、基本は天皇を中心とする律令制の官位であるので、形の上では徳川幕府は朝廷の家臣です。
なので徳川幕府と朝廷は安定した関係を築いて行かなければなりません。
それを江戸幕府が主導で政治を進めて行くためには、天皇・朝廷の権力を抑えてしまうことです。
そのために天皇・朝廷は徳川以外の大名と結託して徳川幕府を倒をさなければなりません。
スポンサーリンク
幕府が上にたった政策
天皇の即位について
第一に天皇の即位について、慶長16年(1611年)の後水尾天皇擁立の際には、徳川幕府の意向に従わせるまでに力の強さを見せつけました。
天皇家の中で不穏な動きがないかどうか、譲位や即位の際もしっかり目を通すことが主な目的でした。
そのために幕府は、朝廷監視の京都所司代を設置し、幕府と朝廷の連絡窓口となる武家伝奏という役職を作っています。
力関係を示す法的根拠:禁中並公家諸法度
これは武家諸法度・元和令と同じく(1615年)に金地院祟伝によって起草されました。
【禁中並公家諸法度】とは
天皇・上皇。公家、問跡(皇族や公家が住職を努める寺社)に対して江戸幕府が定めた規制。
元和元年(1615年)豊臣家を滅ぼし天下を統一した、江戸幕府初代将軍・徳川家康と江戸幕府、第2代将軍・徳川秀忠、前関白・二条昭実の名前で発布されました。
起草者は、江戸幕府の政策担当であった「金地院祟伝」と伝えられています。
江戸幕府が天皇、公家を管理下に置くことを公言して力関係を明確にし、江戸幕府の権力と権威の安定を図ることが目的でした。
事件が起きる
寛永2年(1629年)後水尾天皇が大徳寺などの僧侶に対して紫衣を与えたことにはじまる一連の「紫衣事件」です。
紫衣とは、構僧のみに与えられる紫色の袈裟・法衣のことですが、問題は天皇が幕府に無断で与えたと言う事です。
これがなぜ問題だと言うと、禁中並公家諸法度の中に幕府は、紫衣着用の際には「事前に申し出ること」と規定されていたのです。
この内容を根拠に幕府は、後水尾天皇の勅許を無効にしてしまい、これに抗議した大徳寺の僧侶・沢庵は流罪になった。
後水尾天皇も抗議の意味で、天皇の位を自ら降り、娘の明生天皇に譲位しました。
この一件で、天皇の勅許よりも幕府の意向が上回る、という事を具体的事例と共に世の中に示した訳です。
しかし、幕府は征夷大将軍という官職を利用する以上、朝廷との関係悪化も阻止しなければなりません。
 ▲徳川和子・後水尾皇后
▲徳川和子・後水尾皇后
そのため、元和6年(1620年)7月17日(元和6月18日)に、第二代の徳川秀忠の娘・徳川和子(まさこ)を後水尾天皇に入内※4させています。
※4.入内(じゅだい)とは、皇后、女御となって正式に内裏※5に入ること。
※5.内裏(だいり)とは、古代京都城の宮城における天皇の私的区域のこと。
御所・禁裏・大内などの異称がある。都城の北辺中央に官庁区画である宮城(皇城)があり、宮城内部に天皇の私的な在所である内裏があった。
対外的な関係だけではなく、血縁的にも結びつきを強めることで、より天皇家との関係を深くしたのです。
良好な関係のために
さらに、紫衣事件の後、3代将軍・徳川家光は譲位した後水尾天皇のもとに挨拶に赴いています。
この時、土産として院領として7000石を持参してます。
スポンサーリンク
和子の苦悩
輿入れの当初から徳川和子(まさこ)の立場、ほとんど天皇家と徳川家の板挟みになっていた。
一体何があったのか?
それは一重に「幕府が朝廷に対してアレコレ言い過ぎ」たことです。
例えば、後水尾天皇(ごみずのおてんのう)が他の女性との間に男子をもうけたことに対し、幕府は、「嫁がせる前に、その子を処分(流刑)」にさせてもらう、この時代、乳幼児の死亡率は高く、皇族継統のためには何人子供がいても安心できなかったのに、さすがにこれは横暴な言い分です。
それでなくても禁中並公家諸法度で、「皇室の方々は、こうしてください」とか「公家は、なんたらかんたらすべき」云々と皇室や公家に対し干渉しまくっていた。