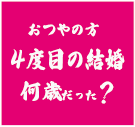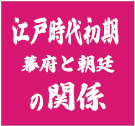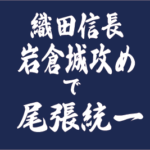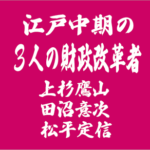上杉謙信は、「義の武将」として知られています。
武田信玄が今川・北条からの経済封鎖で塩の供給を断たれたとき、謙信は「戦いは刀でするものであり、食糧を断つようなことは卑劣である」として、自ら塩を送ったと言われています(「敵に塩を送る」の語源)。
謙信は自らを「毘沙門天の化身」と考え、私利私欲ではなく正義(義)を重んじる戦いをした。
特に関東管領・上杉憲政を匿い、関東の秩序を守るために北条氏と戦った姿勢が「義の戦い」として評価されています。
謙信は戦に勝っても略奪を禁じ、敵将を丁重に扱い、また、生涯妻を持たず、子を作らず、一代限りの主義を貫きました。
一方、織田信長の革新性はというと、戦国時代において鉄砲をいち早く活用し、長篠の戦い天正3年(1575年)では、「三段撃ち」の戦術を駆使して武田勝頼軍を撃破しました。
また、大規模な軍制改革を行い、足軽を中心とした機動力の高い軍隊を編成し、また、楽市楽座を進進し、市場経済を活性化させ、商人を重視したり、既存のの権力構造(寺社勢力や既得権益層)にとらわれず新たな経済秩序を作った。
宗教勢力の比叡山延暦寺や一向一揆を徹底的に弾圧し、既存の宗教勢力の影響力を排除、信長の合理主義的な政治の一環といえます。
信長は「天下布武」を掲げ、戦国大名の中で最も早く中央宗県的な支配を目指し、武家だけでなく商人や技術者を積極的に登用し、身分に関係なく有能の人材を登用しました。
上杉謙信と織田信長が同盟を結ぶ
上杉謙信は享禄3年1月21日(1530年2月18日)生まれ、織田信長は天文3年5月12日(ユリウス暦1534年6月23日)(先発グレゴリオ暦1534年7月3日)生まれの2人がどうして同盟を結んだんでしょう。
上杉謙信と織田信長は、元亀3年(1572年)11月20日に「濃越同盟」を結んだ、この同盟は、美濃の織田信長と越後の上杉謙信の軍事同盟です。
当時の地域情勢
戦国期の東国・中央情勢において、東国では甲斐国の武田氏、相模国の後北条氏、駿河国の今川氏が「甲駿相三国同盟」※1▲を形成し、武田・後北条氏は同盟を背景に北信・北関東において越後上杉氏と敵対していた。
※1.甲駿相模三国同盟とは、攻守軍事協定・相互不可侵協定・領土協定・婚姻の4つの要素から成立し、甲相駿三国においても戦争・和平の要素を満たして同盟関係の成立に至り、東国情勢に大きな影響を及ぼした同盟として機能した。
一方、尾張国の織田氏は、永禄8年(1565年)に将軍・足利義昭を奉じて上洛すると足利義昭を通じて諸大名との外交を展開し、甲斐の武田信玄とは同盟関係を築き越後上杉氏と接触していた。
甲斐武田氏と越後上杉氏の北信を巡る川中島の戦いは、永禄4年(1561年)の第四次合戦を契機に収束し、永禄12年(1569年)末には、織田氏の同盟相手である三河の徳川家康と協調して駿河今川領国への侵攻を開始し(駿河侵攻)、相模後北条氏との関係破綻も招いた。
後北条氏は駿河侵攻後に武田と手切となった徳川家康に加え越後上杉氏との和睦・同盟を持ちかけ(越相同盟)武田氏に対抗する。
武田氏はこれに対して信長・将軍・足利義昭との関係を通じて対抗を図り、越後上杉氏との和睦を開始し(甲越和与)、越相同盟を妨害する。
越相同盟は上杉。北条両者の不和から成立せず、元亀2年(1571年)末には武田・北条間の甲相同盟が回復する。
甲相同盟を背景に武田氏は遠江・三河方面への侵攻を開始し徳川氏と敵対する。
信長は、この殿中御掟などの政治方針をめぐって将軍・足利義昭と対立し、信長打倒を画策した武田氏や越前の朝倉義景、本願寺や北近江の国衆である浅井長政らを糾合※2して信長包囲網を結成した。
※2.糾合(きゅうごう)とは、一つに集めること。「同士をーする」
元亀3年(1572年)信長は甲越和与のため奔走していたが、武田信玄は10月初旬に将軍・足利義昭に応じた三河・織田領へ軍事的侵攻(西上作戦)を開始した。
上杉謙信に対しては石山本願寺や神保氏・椎名氏ら越中の諸将を調略して反乱を起こさせた(越中大乱)。
これにより上杉謙信は越中に釘付け状態となった。
当時、織田軍は朝倉・浅井の他、三好義継・松永久秀ら畿内の諸将による反乱鎮圧にも当たることを余儀なくされ、各地に軍を分散しており武田軍に当たる余力がなく東美濃の岩村城に叔母・おつやの方を遠山景任と結婚させたが武田軍の秋山虎繁に攻められるも援軍を出せず開城してしまった。
挙げ句の果て信長は叔母・おつやの方を処刑してしまった。
※.上記のおつやの方をクリックして頂くと詳しい記事かあります。興味ある方は読んでください。その他岩村城の事が多く書いてありますのでjapan-histrory10 .comをクリックしてください
遠江の徳川家康も10月中旬に一言坂の戦いで大敗し、独力で武田軍に対抗することは不可能でした。
武田信玄の行動に危機感を抱いた、信長は上杉謙信に対して協力を持ちかけ軍事同盟を終結するに至ったのである。
スポンサーリンク
謙信優位の濃越同盟
同盟は元亀3年(1572年)信長が謙信が派遣した使者である長景連※3の面前で熊野午王※4の誓紙に血判を押し、さらに自分の息子を越後に人質として送ることで終結された。
※3.長景連(ちょうかげつら)とは、能登長氏の庶流で、黒滝長氏と呼ばれた。能登・畠山氏臣。後に越後・上杉氏の傘下に入る。
主に外交面で縦横に活躍する。
織田信長の軍勢が上杉方の越中・魚津城を攻略する際、突如として反旗を翻し、わずかな手勢で能登・棚木城に立て籠った。
しかし、織田方長連龍の軍勢に攻められ激戦の末討死した。
これは上杉方の計略とも景連の独断行動とも言われる。
※4.熊野午王(くまのごおう)とは、熊野三山が発行する厄除けの護符(牛王宝印)の中でも最も神聖視されていたものです。
熊野牛王宝印は、75羽鳥の絵を図案化して、「熊野牛王宝印」と記したもので「鳥牛王」おからずさんとも呼ばれています。
鳥は熊野の神の使いと古くから信じられており、起請文※5を書く料紙として用いられました。
※5.起請文(きしょうもん)とは、神仏に誓約する言葉「起請」を文章にした誓約書です。
平安時代後期から江戸時代にかけて作成され、身分職業を問わず広く用いられました。
起請文の構成は、誓約の内容を記した「前書」と、神仏の名を記した「神文」です。
誓いを破った場合は神仏の罰を受ける旨が記されており、神仏への証文として用いられました。
「長与市(景連のこと)参着。信長則ち公(謙信)の諜書を被閲し、景連に会面して、渠※6眼前に追て牛王宝印を翻し、血判をそそぎて返簡をわたさる」(北越軍談)。
※6.渠(きょ)とは、人工の水路、掘り割り、みぞ。かしら、首領。三人称の代名詞。
疑問・反語を示す除学。建築や土木分野では、人工の水路を意味する言葉として使われます。
ただし、この同盟は対等な同盟ではない、相質(人質交換)をしておらず、信長だけが上杉に人質を出している謙信優位の軍事同盟であった。
スポンサーリンク
謙信・信長の濃越同盟終焉
武田信玄による西上作戦は、元亀4年(1573年)4月に信玄死去による撤兵され収束される。
濃越同盟は、その後も継続され信長は謙信に対して贈答品を送っています(南蛮式のマントなど)。
天正4年(1576年)には、安芸国※7・毛利氏のもとに亡命していた足利義昭による反信長勢力の糾合※8に応じ、本願寺は信長に対して挙兵(石山合戦)。
※7.安芸国(あきのくに)とは、現・広島県西半部を占めていた旧国名です。
律令制下では山陽道に属し、芸州とも呼ばれました。
安芸国の歴史は、平安時代に菅原道真が編纂した「延喜式」に多家神社、伊都岐島神社(厳島神社)、速谷神社が名神大社と記されています。
久安2年(1146年)に平清盛が国守となり、平氏にとって重要な知行地となった。
鎌倉時代以降、小早川氏、吉川氏、毛利氏などの東国御家人に移住し、在地領主制が展開されました。
戦国時代には、毛利元就が中国地方全域を統一。
明治4年(1871年)の廃藩置県により広島県が成立し、安芸国は広島県となりました。
安芸国の国府は、現在の安芸郡府中町、国分寺は東広島市西条町にあります。
※8.糾合(きゅうごう)とは、一つに集めること。「同士をーする」。
長島・越前と破滅して追い詰められていた本願寺の顕如は、信長に対抗するため上杉謙信の祖父・長尾能景時代から敵対関係にあった上杉氏との和睦を模索する。
同年5月に将軍・足利義昭は、上杉・武田・北条三者の和睦を調停し、(甲相越一和)、三和は失敗に終わるが織田・上杉間の関係は多く変化する。
北陸の一向門徒らも上杉謙信に助力を求めたため、同年5月18日に上杉謙信と顕如は和睦し、同盟を結んだ(『上越市史』別編(上杉氏書集)・1289号))。
これにより、濃越同盟は消滅し、謙信と信長は敵対関係になった。
スポンサーリンク
手取川の戦い
この戦いは、間接的(信長は出陣してない)ながら天正5年(1577年)に友好関係にあった上杉謙信と織田軍の総大勝・柴田勝家の戦いです。
戦いの背景には、北陸地方における両者の勢力拡大があります。
経緯は、能登の七尾城の守護・畠山義隆が天正2年(1574年)に死去し、幼児・畠山春王丸が跡を継いだ。
天正4年(1576年)、越後国の上杉謙信は能登の国を支配下に置くべき、2万余の軍を率いて侵攻、これに対して当時の能登の領主・能登畠山春王丸(まだ幼児だったため重臣の長続連・長綱連父子が実権を掌握)は七尾城に籠城、堅城だったため戦いは翌年まで続いた。
天正5年(1577年)、関東で北条氏政が攻勢、関東諸将から救援要請を受けた謙信は一時春日山城に撤退。
上杉軍が奪った城冨木・熊木が落とされた、更に7月18日、長綱連が穴水城を攻めると、上杉軍の重臣・能登甲山城の平子和泉は、救援向かわせたがこれを長連龍が水軍を率いて迎撃し、乙ヶ崎合戦で大勝した。
翌、織田信長は、奥州の伊達政宗らと越後の本荘繁長と諜り、謙信を討つ相談をしてた。
長続連は、上杉軍に対抗する畠山春王丸は病死畠山軍は危機的状況に陥った。
長続連は、信長に援軍を求めると、柴田勝家を総大将して、8月8日に北国に向けて出陣するも大敗する。