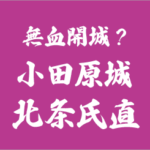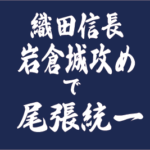庶民に愛される賓頭盧(びんずる)尊者像は病を治してくれる「なで仏」として庶民に知られています。
令和5年4月5日の午前8時45分頃、長野市の善光寺の本堂から、触ると病気が治ると親しまれている「びんずる尊者像」が盗まれた。
「びんずる様」ってなんだろう思う方も多いと思いますが、知ってるしとは知っています。
お釈迦様の弟子で、16羅漢の一人です。
神通力をもて遊んだとしてお釈迦様に叱責され涅槃※(ねはん)を許されず、お釈迦様の入滅後も衆生の救済にあたった。
※涅槃(ねはん)とは、サンスクリット語でニルヴァーナと言い、全ての煩悩の火が吹き消された状態、すなわち安らぎ、悟りの境地を指しています。また、生命の火が吹き消されたということでもあることから、入滅、死去を意味し、お釈迦さまが亡くなられたことを「涅槃に入る」と表現します。
スポンサーリンク
日本では堂の前に置き、これを撫でると除病の功徳があるという俗信が広まった。
とても難しい顔をされているびんずる様ですが、赤いベレー帽をかぶったその姿は見ている間に何だか優しいお顔にも見えてくるから不思議です。
病を患っている場所と同じ部分をなでると病気が治るのだそうです。
そういう理由で「なで仏」とも言われます。
 ▲これは東大寺のびんずるさんです。
▲これは東大寺のびんずるさんです。
 ▲東大寺
▲東大寺
といっても実際は足や手は何とか届くのですが上の方までは届きません。左肩を痛めている私ですが肩まで届かず撫でることができませんでした。
びんずるさんとは?
16羅漢の一人で、サンスクリット語では、ピンドーラ・バーラドヴァージャといわれます。
漢字で音写すると、賓頭盧 頗羅堕(びんずる はらだ)となります。
賓頭盧が名で、頗羅堕が姓です。
賓頭盧さんは、獅子吼※1第一と呼ばれ、神通力=超能力がとても強い人だったといわれています。
※1.獅子吼(ししく)とは、大いに雄弁を振るうこと。大演説。▲
ある時、お賓頭盧さんは人のすすめに乗り、神通力を使って座ったまま高いところにある栴檀の鉢を取って見せました。
この行いを知ったお釈迦様は、修行者らしからぬ事をしたと叱咤され、賓頭盧さんは退けられて、閻浮提※2を去り、西午貨洲※3に移り人々を強化したといわれます。
※2.閻浮提(えんぶだい)とは、須弥山の南方にある国。もと、インドの称であったが、人間世界の称となり、また現生の称となった。
※3.西午貨洲(さいごけしゅう)とは、仏教的宇宙観で、須弥山の四方にあるある島を四大洲といいます。また、四天下などと呼ばれます。
また、次のような話もあります。
正法が尽きるまで涅槃に入らぬようにと、お釈迦様から命じられ、摩梨山にすみ人々の教花に務めた。
国王や長者たちはお賓頭盧さんによく食などの供養をした。
食堂から外陣に祀る
賓頭盧さんは、優れた人だったので、中国では470年頃から聖僧として、お参りされる対象となり、次第にお寺の食堂(じきどう)に祀られるようになりました。
日本では食堂から、いつの間にか本堂の外陣や回路に祀られるようになり、病んでる場所をと同じ所を撫でて治す、と言うような風習が出来上がりました。
賓頭盧さんは木像が多いのですが、沢山の人が撫でるので、像はピカピカに磨かれて銅像のように見えたり、中には表情がほとんど分からない程、摩耗してる像もあります。
また、賓頭盧さんは病気を治すだけではなく、亡くなった人を供養する役割や、厄祓いの役割を担っています。
金箔を貼って・・・治す
現在では、患部とと同じ所を撫でて治るように祈りますが、当初は紙で賓頭盧(びんずる)さんを撫で、その紙で自分の患部を撫でているようです。
直接撫でるようになったのは、江戸時代中期からのようです。
この撫で仏の原型とも思えるような話が、大唐西域記の一番最後の部分、瞿薩旦那国(くさたなこく)の紹介の中に登場します。
栴檀の木で造られた高さ6m程の仏像があり、大変霊験があって光明を放っていました。
この仏像に患部と同じ場所に金箔を貼ると、すぐに病が治るとされていました。
そして、この仏像を崇拝した羅漢さんや、その羅漢さんが困った時、食物を与えた親切な人達がいたこと、その親切な人達は、羅漢さんの予言で災いを避けることが出来たことなど、仏像→羅漢さん→お賓頭盧さん、食に困らない、災いを除く、病を治すなど、何か繋がりを感じさせる話です。
スポンサーリンク
お釈迦様に叱咤され西午貨洲に移った
仏教的宇宙観で須弥山の四方にある四つの島を四大洲といいます。四洲、四天下(してんげ)などとも呼ばれます。
四つの大きな島
一つの島の大きさは8,500K㎡〜2億4,000万K㎡です。
地球の陸地の合計が約1億4,800万K㎡といわれていますから、島というよりは大陸と追った方がいいかもしれません。
四つの島には次のような名前がついています。
○東勝身洲(とうしょうしんしゅう) (弗婆提 ほつばだい)ともいわれます。
この島の名前の由来:勝れた身の形をしているので勝身洲と名づけられました。
○南贍部洲(なんせんぶしゅう)(閻浮提 えんぶだい)ともいわれます。
この島の名前の由来:贍部はジャムブの音写です。
贍部と閻浮は音写の違いです。
提と洲は音写か意訳かの違いです。
ジャムブ樹と呼ばれる大木が、沢山生えている島ということで名づけられました。
現在のインドにもジャムブ樹と呼ばれる木があります。
○西牛貨洲(さいごけしゅう)(瞿陀尼 くだに)ともいわれています。
この島の名前の由来:牛を貿易するので牛貨洲と名づけられました。
○北倶盧洲(ほくくるしゅう)(鬱単越 うったんおつ)ともいわれています。
この島の名前の由来:別名の鬱単越は勝処と訳します。
四洲の中で最も勝れた国土なので勝処と名づけられました。
※.四大洲には、それぞれ二つの中洲と500の小洲が付属しています。四大洲と中洲には人が住み、小洲には人が住んでいない島もあります。