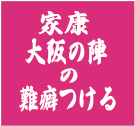頼朝の女好きが政子を恐妻にしてしまった。
”鎌倉殿の13人“で、亀の前と頼朝が深い関係であったと記憶してしている方が多いと思いますが、どいう女性だったのか、あまり深くは知らない。
そこで調べました。
愛妾「亀の前」という女性
この亀とは、どのような女性だったか?
亀の前は、頼朝が伊豆国での流人暮らしの頃から仕えてた良橋太郎入道の娘。
この良橋太郎入道とはいかなる人物かというと、『吾妻鏡』によれば、その名の「良橋」から下総国吉橋郷(現・千葉県八千代市吉橋)の領主であった可能性を指摘する向きもあるが、実際のところは不明です。
さほど身分の高くない人物だった。
亀の前のことを「顔㒵之濃かなるのみに匪ず」こう言ってる、顔㒵(がんぼう)之濃(こまや)かなるのみに匪(あら)ず。
ようするに「容貌が整っているだけではなく」、「心操(こころばせ)殊に柔和也」すなわち「性格が特に柔和出あった」と記している。
また、『吾妻鏡』によると、豆州(現・伊豆)に、御旅居※1がいた頃からの昵近※2であり、寿永元年の春から密通していた。
※1.御旅居とは、自宅を離れて他の場所にいること。また、旅のすまい。たびずまい。「例の家にもえ行かず、すずろなるーのみして」
※2.昵近(じっきん)とは、 (━する) なれ親しむこと。多く、貴人に親しみ近づくこと。また、なれ親しんでいる相手の人。
頼朝とのなれはじめは、史料ではこのように記されるだけで、つまり出自など正体は判然としない女性といってもいい。
どのような「素性であるにせよ、寿永元年の時点で、頼朝は妾として寵愛していたことは事実」だけど、政子は知らなかった。
頼朝は亀の前を気に入って、寿永元年(1182年)の春頃から密かに亀の前を鎌倉に呼び寄せて寵愛した。
この亀の前のことが政子に発覚するのは、頼朝の正室・北条政子が次男・万寿(のちの源頼家)を妊娠中の同年6月、日を追って寵愛が増したきた、頼朝は亀の前を、鎌倉の位置する小坪(現・逗子市)の中原光家の屋敷に呼び寄せて住まわせた。
それは妻に発覚を気遣って居所を遠くに構えたという。
頼朝でも妻・政子が怖かったからなのか、それとも単に外聞を憚ったのか?
その後、頼朝は亀の前を飯島(現・逗子)の伏見広綱の屋敷へ移して、逢瀬を続けた。
8月12日に政子は出産、待望の跡取り誕生したのにもかかわらず、妻・政子を労うどころか、亀の前に入れ上げ寵愛は日増しに半ば公然の関係になっていった。
後妻打ちの結果
この事を継母の牧の方から知らされる。
聞いた政子は激怒し、11月10日牧の方の(兄か父)の牧宗睦に命じて伏見広綱宅を破壊する。
後妻打ち(うわなりうち)を行い、大いに恥辱を与えるつもりが大事になった。
「後妻打とは、前妻が親しい女たちをかたらって後妻を襲い、家財などを打ちこわし
濫妨※3を働く事をいう。
※3,濫妨(らんぼう)とは、正当な理由なしに他人の所領知行を妨害すること。▲
『昔々物語』によれば後妻打ちは、男性が妻を離別して1ヵ月以内に後妻を迎えた時に使われる。
まず前妻方から後妻の家に使者をたて、何月何日に後妻打を行うこと、使用する道具などを通告して行う。
頼朝の場合は最初は流人であったが、今や頼朝は武家の棟梁となっている。
一方政子は、坂東の豪族の娘にすぎない、頼朝と身分的に不釣り合いになってしまったということは、政子が正室の座から引きずり降ろされても不思議ではない、そんな焦りが政子を過激な行動に駆けたてた。
亀の前は広綱宅に連れられ、命からがら鐙摺(あぶすり:現・葉山町)の大多和義久の屋敷へ逃げだし、別の人物の家に隠れた。
愛妾への暴挙を知った頼朝は、烈火のごとく怒ったが、御台所の政子に罪を負わせる訳にはいかない。
その結果、実行犯の牧宗親を公衆の面前で叱りつけ、髻※4を切り取ってしまう。
※4.髻(もとどり)とは、まげの頭頂部分。▲
『吾妻鏡』の記述によると、「御台を重んじたのは結構なことだ。だけど、御台の命令に従うといっても、こいう時は、まず、こっそりと俺に知らせよ」と勝手なこといった。
一方、政子の父・時政は妻の父・牧宗親を辱められ、頼朝に対して怒り心頭だったため、無断で鎌倉を離れ、領地のある伊豆へ帰ってしまう。
慌てふためいた頼朝は、時政の子・義時に動向を見に行かせた。
義時は父に同調せず、鎌倉に留まってくれた、頼朝は義時をますます信任するようになった。
都育ちの御曹司頼朝と坂東育ちの政子の違い
事件を通じてわかることは、源頼朝は女好きであり、一方対する政子は嫉妬深い激情型ということ。
頼朝は政子のそうした性格を知っていながら、女癖が治らない、どうしてかというと都育ちの上高貴な家柄の御曹司、妾を持つなど当たり前だったからです。
片や伊豆で育った田舎娘の政子は、夫が妾を囲うことなど許せないことだった。
頼朝の女好きは度を越えていると思ったに違いない。
ましてや頼朝の嫡男を産んだ同年8月12日、そんな日に亀の前と密会してたことは、気性の荒い政子にとっては許し難い出来事であった。
誰もが頼朝より政子の悋気※5を怖れていた。
▲※5.悋気(りんき)とは、嫉妬。▲
その後も頼朝は懲りずに浮気を繰り返し、頼家の4つ下には御所の侍女の産ませた男児・貞暁がいた。
その貞暁が7歳になっ建久3年(1192年)に乳母を決める際、政子の嫉妬を怖れて悉く辞退、人選に苦慮している。
貞暁・母子は政子から逃げるために京都へ、貞暁は生後すぐに仁和寺に預けられ、さらに、高野山に逃れ、行勝上人の元で修行に励んでいました。
後で政子(尼将軍)になって高野山まで、会いにいってる。(後日記事を書く予定)
頼朝にとっては一夫多妻の考えでいたけど、当時の軍事貴族の習わしで妾を持っただけに、妻・政子が常軌※6。
※6.常軌(じょうき)とは、つねにふみ行うべき道。普通のやり方や考え方。常道。「◯◯を失った行動」
ついでに触れておくと、頼朝は、この頃、亀の前だけでは飽きたらず、同じ清和源氏一族である新田義重の娘にも懸想していたらしい。
新たな浮気相手を選んが相手にされず
『吾妻鏡』によれば、政子が出産した翌々日、新田義重が頼朝の不興※7をかったとの記述だある。
※7.不興(ふきょう)とは、興味がなくなること。しらけること。また、そのさま。興ざめ。「座が不興になる」▲
その名は、祥寿姫(生没年不明:しょうじゅひめ、生没年不詳)は、平安時代末期の新田氏一族の女性。源義重の娘。源義平の正室。実名は不明。
夫である源義平は平治元年(1159年)12月の平治の乱で敗れたのち、翌年1月に捕らえれて斬首され、源(新田)義重の娘は未亡人となる。
平治の乱から、20年後の治承4年(1180年)8月、源義平の異母弟源頼朝が挙兵して東国の主となると、去就※8を迷っていた父・義重は参陣が遅れ12月になって鎌倉を訪れたため、頼朝の不興をかった。
※8.去就(きょしゅう)とは、どう身を処するかの態度。進退。「今後の身を○○にまよう」「○○を決する」
『吾妻鏡』によると
寿永元年(1182年)7月14条によると、頼朝は伏見広綱に命じて、密かに兄の未亡人である義重の娘に艶書を送っていたが、義重の娘は全く受け入れる気配なく、頼朝は直接父の義重に申し入れたところ、政子の怒りを畏れた義重は娘を、すぐさま師六郎という者に嫁がせたことから、頼朝の勘気を被ったという。
この事が頼朝による後の新田氏冷遇に繋がったとされている。