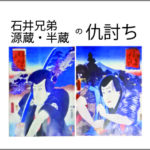天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦い後、調和条件として秀吉のもとへ養子を差し出すことになった家康。
当初は、家康の異父弟にあたる松平定勝(実母・於大の方と再婚した久松俊勝の子)を送ろうとするが、於大の方が猛反対によって中止、それにより家康の子・於義伊(秀康)が選ばれてしまった。これが悲運の始まり。
では何故、於大の方は反対したかと言うと、過去に永禄6年(1563年)に家康の命で今川氏真の元に人質に入るが、武田信玄の駿河侵攻によって松平康勝を武田方に連れて行き人質となった。
スポンサーリンク
元亀元年(1570年)に、逃げ出してきたが両足の指を凍傷で失った経過があったので反対したため、家康の次男・義伊松が養子に出される。
その時、家康が餞別として童子切安綱を義伊松(秀康)に持たせたとされてますが‥.
と書いてありますが、実際には「童子切」を第2代の将軍・秀忠の娘・勝姫(天崇院)が松平忠直へ嫁がせる際に守り刀として持たせたものであるという。
見送られた義伊松は、大阪に着いて秀吉に挨拶すると秀吉は忠光作の佩刀を受けたという。
この忠光は出羽守直政(出雲国松江城初代藩主)へと伝わったとされます。
スポンサーリンク
最古の刀工の傑作
太刀の分類
太刀とは:現代では刀身が2尺以上(約90cm)未満のものを指します。
大太刀とは : 野太刀とも呼ばれ、刀身が3尺以上の太刀を指し、大型のものでは、10尺(約3.3m)以上になるものが存在する。
鎌倉時代に好んで作られたが、後に摺り上げられて通常の長さに直されてしまってもの多く、現存するものは少ないと言われています。
小太刀とは:刀身が2尺未満のもの、形状は直接的ものが多いので、現代では脇差との違いは曖昧であり、その存在理由については各説があります。
スポンサーリンク
童子切安綱
太刀です。
銘:安綱(名物・童子切)※名物とは、日本刀において特に姿が優れたものを指す。茶器においても名物、大名物の名称が用いられます。
刃長80.0cm、反り2.7cm、元幅2.9cm、先幅1.9cm、鋒の長さ3.1cm
国宝です。
国立文化財機構所蔵(東京国立博物館保管)
源頼光
頼光四天王を引き連れ丹波大江山の酒呑童子の首を切り落とした時の剣といわれています。
酒呑童子退治の逸話と共に広く知られています。
それによると、頼光が四天王と共に大江山に棲むと言う鬼を退治するため向かい、途中で三人の翁(熊野、住吉、八幡)に出会う。
翁たちは、頼光たちに「神便鬼毒酒(じんべんきどくしゅ)神変奇特酒(しんべんきどくしゅ)とも)」、打銚子(うちでうし)(ながえのてうし)、星兜(ほしかぶと)または帽子兜(ぼうしかぶと)ともいう、酒を授ける。
スポンサーリンク
「神便鬼毒酒」は、人が飲めば千人力の薬となるが、鬼が飲めば飛行自在の神通力を失うという。
また、「打銚子」は神便鬼毒酒を入れる銚子で、昔神世の時に、この銚子で酒を飲ませることにより鬼を平らげたとするもの。
最後の「星兜」は、昔神軍が悪魔を鎮める時に「正八幡大菩薩が召したもの」であるという。
頼光一行は山道を進み、鬼が城に辿り着き山伏に化けて酒盛りを聞かせ、「神便鬼毒酒」を飲ませ、体を動かなくしたうえで神殿で寝ていた童子の寝首を安綱の太刀で掻いたという。
首は頼光の兜に食らいつくが、十二枚貼りの星兜により一枚だけ残しなんとが無事であったという。
外にでると茨木童子が襲い掛かってくるが渡辺綱がこれを倒す。
さらに石熊童子や星熊童子、虎熊童子なども退治したという。
これより後、この安綱の太刀は「童子切」と呼ばれることとなった。