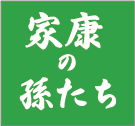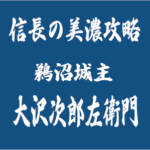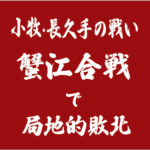こんにちは隆太郎です。
皆さんもご存じのように、家康の長男は信康、信康は正室・瀬名から生まれたが父親に命を奪われた。
三男の・秀忠が生まれた年は、天正7年(1579年)で、当時、織田信長が安土城の天守を完成させ天下統一に邁進していた時でした。
同じ時季に、結城秀康の兄・信康、築山殿事件が起こり、長男・信康は1559年生まれ、次男・結城秀康は1574年生まれなので15歳の差、三男・秀忠は1579年生まれで信康とは20歳の差、次男・秀康とは5歳の差。
◇信康の母は、正室・築山殿。
◇結城秀康の母は、側室・お万の方(長勝院)、家康の正室・築山殿の侍女で築山殿に仕えていて二人の子供を授かりますが、築山殿からは歓迎された出産ではなかった。
◇秀忠の母は、初名はあい、お愛とされるが、お相が正しいという説があります。
側室・西郷局と称した。他に松平忠吉を産んだ、父は戸塚忠治、母は源姓土岐氏流三河西郷氏とされ西郷正勝の娘とされる。
家康の跡を継ぐのは、順番からいうと長男・次男・三男という順に決まるが、二代将軍になったのは三男の秀忠だった。
では何故次男の結城秀康が将軍になれなかったか?
スポンサーリンク
秀康が将軍になれなかった理由
家康の次男・義伊松(結城秀康)が養子に出された理由は、ことの起こりは、織田信長の跡を継ぐために織田信雄と羽柴秀吉が戦った。
天正12年(1584年)に起きた小牧・長久手の戦いです。
豊臣秀吉と織田信雄or徳川家康の戦いでしたが、織田信雄が勝手に秀吉と和議をしてしまったため戦いは終わった。
局地的には家康の方が勝利を得たものの大義名分がないのと、物量に勝る秀吉には勝てず和睦を選択、そして家康が秀吉の条件を聞いて和睦条件を飲む、条件は人質として、長松(後の秀忠は5歳だったため)兄・義伊松(後の結城秀康は10歳)が秀吉のもとに差し出されてしまう。
当初は、家康の異父弟にあたる松平定勝(実母・於大の方と再婚した久松俊勝の子)を送ろうとするが、於大の方が猛反対によって中止、それにより家康の子・於義伊(秀康)が選ばれてしまった。
ここから於義伊(秀康)の悲運が始まった。
家康も、この頃は正室に遠慮があったかわからないが、正室の侍女に手をつけてしまった。
普通なら側室として認める訳ですが、築山殿が侍女のお万が子供を産んだため、築山殿が認めないので、また家康も認知出来なかった。
そのため於義伊、於義丸、義伊丸、義伊松(幼名)(後の羽柴秀康、秀朝、結城秀康)と名前、満3歳になるまで対面を果たせなかったため、あまりの冷遇を受ける異母弟を不憫の思った長男・松平信康が対面を取り計らったが、家康の子として認知されなかった。
そして、天正7年(1579年)武田勝頼との内通疑惑から信康は切腹、正妻の築山殿は暗殺で幕を閉じた。
築山殿がが死去してから、幼名・義伊松(秀康)は家康の子として認知され、その間、10歳になるまで宇布見村にて中村源左衛門や本多重次のもとで育てられ武士としての心得や作法、武芸など叩き込まれたという。
スポンサーリンク
羽柴家(豊臣家)の養子となる
いよいよ大阪へ行く供は、石川康勝※1と本多成重※2が従った。
※1.石川康勝とは、信濃奥仁科藩主。石川数正の次男。
※2.本多成重とは、越前丸岡藩の初代藩主。徳川氏の家臣、本多重次の長男。
家康は、名刀「童子切」の刀と采配を餞別として渡したと言われるが‥
※.上記の童子切をクリックして頂くと詳しい記事があります。興味のある方はご覧になってください。
義伊松(幼名)は、秀吉の養子となり、秀吉の名前と家康の名前を貰って秀康と名乗るようになります。
その時に秀吉が書いた公文書の中に、秀康は「家康嫡子」とかかれており、、元服した後も「徳川三河守」と書かれています。
つまり秀吉のもとに人質として入った時点では、義伊松(秀康)は家康の後継ぎとして見られていた可能性が高いことが分かります。
天正12年(1584年)12月12日、羽柴秀吉の養子として「羽柴三河守秀康」と名乗って、河内国に1万石を与えられた。
『国事叢記』によれば、このとき、従五位下三河守となり、天正13年(1585年)7月11日、秀吉が関白に任じられたとき、秀康は従四位下侍従。
天正16年(1588年)、正四位下左近衛権少将となった。
一方、「結城系図」では、天正12年(1584年)、従四位下侍従に就任、天正13年(1585年)7月11日、左近衛少将・三河守となっている(黒田基樹は、天正13年10月4日、侍従に任官としている)。
「結城系図」でも、「異本云」として、この日7月11日、従四位下侍従兼三河守となり、天正14年に正四位下左近衛少将となったことを記載している。
なお、秀吉は、家康が上洛しないので秀康に対して、「義父・秀吉は秀康を殺害しようとしている」との流言も上がった。
なんとしても秀吉は、家康と主従関係をとりたいと考え、家康を妹・婿とすることで形式的な従属を強めようと考えて実行した。
天正14年(1586年)、秀吉は政略結婚のために強制的に妹・朝日姫を離縁させ4月に大阪城を出て聚落第に入り14日に浜松に至って家康の正室となった。
家康45歳、朝日姫44歳だった。
家康は婚儀が済んでも上洛しなかったため、大政所が岡崎の駿河御前を訪ねるいう形でさらに人質となり、家康はやっと上洛して秀吉との和議が成立した。
秀康の初陣
天正15年(1587年)、14歳の時、九州征伐で初陣を果たし、豊前国岩石城攻めで先鋒を務めた。
続く日向国平定戦でも抜群の功績を挙げた。
天正16年(1588年)豊臣姓を下賜※3された。
※3.下賜(かし)とは、身分の高い人からくだされること。くだし賜ること。
また、秀康は4月までの時点で左近衛少将・三河守に任官し「三河少将」と呼ばれた。
スポンサーリンク
秀吉のワガママで養子を解消
天正17年(1589年)、秀吉に実子の鶴松が誕生すると、秀吉は鶴松を生後4ヶ月で豊臣氏の後継者として指名したため、養子縁組をしてた者は他家に出された。
こうして豊臣秀吉の養子となった義伊松(羽柴秀康)ですが、さらに秀康の立場を複雑にしてしまった結城家への養子入りが決まった。
スポンサーリンク
じゃどうして結城家に行ったか
結城家はどういう家柄か?というと、結城家の起源は古く、平将門を討った藤原秀郷の末裔で、発祥地は、下総国結城郡(現・茨城県結城市)で地頭を務めた、ときから(結城姓を名乗り)鎌倉幕府の御家人だった結城朝光を祖とした。
戦国時代に、結城晴朝の父・結城政勝の代に勢力を拡大、天正18年(1590年)7月小田原征伐後、秀吉は奥州仕置きのため宇都宮に行き、この際、結城晴朝が宿泊の接待をし、秀吉に豊臣家一族を養子に欲しいとの話を持ち出した。
秀吉は承諾し、秀康が結城晴朝の孫娘(江戸重道※4の次女)と婚姻して結城家の家督を継ぐこととした。
※4.江戸重道とは、常陸江戸氏9代当主。常陸国水戸城主。常陸江戸氏は常陸の国人。藤原北家魚名流とされる藤原秀郷の後裔・川野辺氏の支流である那珂氏の傍流。
同年8月6日、秀康は結城城に入り、結城領10万1000石を継ぎ、養父・結城晴朝は栃井城に移った。
その後も秀康は羽柴姓を称しており、羽柴結城少将と呼ばれた。
結城家を継いだ後、葛西大崎一揆鎮圧のため奥州に出陣し、天正20年(1592年)からの文禄・慶長の役にも参加。
文禄元年(1592年)、文禄・慶長の役では、多賀谷三経や本多冨正など1500人を率いて肥前国唐津に滞陣した。
25歳になった秀康は、慶長4年(1599年)から慶長5年(1600年)6月まで伏見城を守備し、同年6月8日は伏見を発って関東に向かい関ヶ原の戦いの前哨戦である会津征伐に参戦。
上杉景勝に呼応する※5かたちで石田三成が挙兵すると、家康は小山評定を会議開いて諸将とともに西上を決める。
※5.呼応するとは、一方が呼びかけたりしたことに対して相手が答えること。お互いに気心が通じあうこと。互いに気脈が通じて物事を行うこと。
※.上記の小山評定をクリックしていただくと詳しい記事があります、興味ある方はご覧になってください。
この時、家康によって本隊は家康自らが率いて東海道から、そして別働隊を秀忠が率いて中山道(東山道)を進軍することが決められ、結城秀康は宇都宮に留まり上杉景勝の抑えを命じられた。
同年9月7日、徳川家康が伊達政宗に宛てた手紙には、次男・秀康と相談して上杉軍に備えるよう指示していることから、家康は秀康の武将としての器量を評価しており父子がそれぞれの立場をわきまえて生涯認めあっていたことは確かである。
スポンサーリンク
越前に移封した訳
慶長5年(1600年)11月、結城秀康は越前国北ノ庄68万石余に加増された、越前の他、信濃国、若狭国の一部)。
そして旧来の家臣の中には越前の移転を拒否する者も少なくなかった。
慶長6年(1601年)8月14日頃、北ノ庄に入部した。
越前国北ノ庄藩(福井藩)初代藩主。越前松平家の祖で結城氏第18代当主。
なぜ家康は息子秀康を越前国を与えたのか?
関ヶ原の戦いの後、勝ったといえども脅威が残っていた、いまだ健在の豊臣家、三成は討ち取ったが豊臣家には強大な財力があり、各地に秀吉の小飼の武将たちが健在で残っていた。
一つは、加賀前田家の強大な軍事力、能登、加賀、越中の3ヶ国の100万石を超える豊かな大名・前田家は徳川家を脅かす存在、軍事力だけではない他の大名に与える影響力を持っていたからである。
それと、もう一つは朝廷、天皇の威光は絶大なもの、その天皇の元に仕える公家、その公家を利用して徳川家に敵対する武将だけではなく、日本国民までが徳川家を認めないことには天下を取ったことにはならない。
家康が考えた事は、前田家と豊臣家、そして朝廷が手を結ぶことを恐れたので、家康が信頼する武将を加賀前田家の近くに置き監視徹底する事でした。
豊臣家を監視するのは彦根の井伊直政、朝廷に対しては若狭の京極隆次を配置した。
京極家は室町幕府からの名家で本来は近江国を支配していました。
井伊直政と仲がよく京都・公卿補佐を務めていて公家や公卿との関係性が強かった大名でした。
加賀前田家の監視役を家康から仰つかったのが結城秀康です。
結城秀康は負けん気が強い男で関ヶ原の戦いで上杉景勝に挑戦状を送るなど、他の大名にも引けを取らない度胸があるので監視役として越前北ノ庄藩(福井藩)に配し、目的は監視で越前に移封させた。
秀康は、まず越前に入ると加賀との国境に近いあわら市細呂木地区に関所を設け重臣・多賀谷三経にあわら市柿谷地区付近に3万2000石与え、その家臣は200人のものぼったため、加賀前田家は江戸や大阪、京都へ行く時は細呂木の関所を通らなければならず徹底にチェクをした。
前田家の対応は早く、前田利家の正室・まつ(芳春院)が人質として徳川家に服従したため前田家の監視はやめて、大阪の豊臣家に移った。
慶長11年(1606年)4月に越前で死去34歳の若さ死因は梅毒。