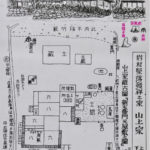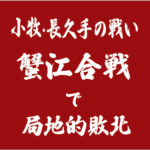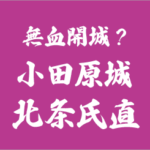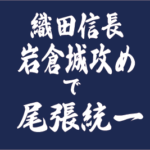源頼朝が平家を倒して鎌倉幕府を開いた。
いままで朝廷にこき使われていた武士が、平家を倒しては武士が頂点に立つ政治を行う体制に持って行ったのです。
でも頼朝の死、子頼家・実朝が死んで頼朝の直系の血筋の将軍が途絶えてしまう。
千鶴丸が生きていれば歴史は変わったはず。
スポンサーリンク
父の執権を反面教師に改革
父・北条時政を追放してから、義時は政子と協力して鎌倉幕府を盛り上げて行った。

▲北条義時(イメージ)
義時は父が就いていた幕府の政治の中枢を担う、政所の役を受け継ぎ将軍を補佐する執権として権力を振るった。
執権になったはいいが、「幼い第3代の源実朝を将軍に置いて政治の実権は北条氏が握る」という父のやり方に躊躇した。
なぜかというと父・時政は実朝を全く無視して俺の天下だ〜と言わんばかりに独裁者のように振る舞ってたことを義時は改めることにした。
父の時政は執権として絶大な権力を持ってたので、娘婿の平賀朝雅を将軍にしたいとという野望を持ったに違いない、あくまで北条は将軍の補佐役にすぎないのです。
実朝を裏で操りながら、将軍の名でいろいろ決定や命令を下すことで権力を持つことができていたわけです。
それが時政は次第に実朝の名を使わず、自分の名で下知条という文章を作り、御家人たちに対してさまざまな決定・命令を与えるようになってきた。
時政は実朝はわしの操り人形、だからわしの命令でも実朝と同じだ、逆らう御家人もいないし命令に従っていればいいんだ〜と言って、この露骨な時政を御家人は不満を持ちました。
こうして父は人望を失い義時の手によって失脚したわけです。
北条義時は父と同じにはならない、命令は実朝の名で下すように改善して、失われた北条の執権職を取り戻そうとしました。
そのために政子の力を借りながら強大な権力を誇示しつつも、それに決して驕ることなく、御家人たちにも譲歩する柔軟さを示しました。
利害関係が複雑で実力がモノをいう鎌倉幕府では、人間関係に敏感だったり交渉ごとが上手くないと権力の座に立ち続けることはできません。
義時は直感的に思った。
第2代義時の執権政治はどう変わったか
基本的な政治体制は同じ、北条氏繁栄の邪魔になる存在はどんどん排除していきました。
ただし父のような強引な手は使いませんが、機を伺い慎重かつ計画的に敵を潰していくという手法です。
なるべくできる限り無駄な敵を作らない、これは父を反面教師にしてできる限り無駄な敵を作らないようにしました。
義時が敵にしたのは、和田義盛という鎌倉殿の13人のメンバーだった一人、鎌倉幕府の重鎮で侍所※1のトップだった人物。
※1.侍所とは、御家人の統率・管理や警察の仕事を担う部署。
侍所は軍事力を掌握できる点で、義時がトップに立っている政所に匹敵する影響力を持っていましたので、権力が欲しい時に必ず障壁となるのが侍所のトップである和田義盛だった。
この和田義盛を失脚させたいと密かにチャンスを狙い定めてチャンスを待っていましたら、建暦3年(1213年)にやってきました。
和田義盛の反乱です。
北条義時を排除しようと企む泉親衛の謀反が露見、その折に和田義盛の息子の義直、義重と甥の胤長が捕縛される。
その後、息子の二人は配慮され赦免される。
義盛は三浦を含む一族を挙げて甥の胤長も赦免を懇請※2したが、胤長は首謀者格と同等のため許されず流罪となった。
※2.懇請(こんせい)とは、心を込めてひたすら頼むこと。
さらにその後、胤長の屋敷が没収されてしまった。
これらの件で両者の関係は悪化、鎌倉幕府創業の功臣であり侍所別当の和田義盛は同年5月に、親戚関係にあった横山党や同族の三浦義村と組んで北条氏を打倒するための挙兵をした。
ただ、土壇場で三浦義村は御所側へ付き和田を裏切ったため、兵力不足のまま和田一族は将軍御所を襲撃、鎌倉で市街戦が始まったが、合戦は2日間続いた、将軍・実朝を擁し兵力で勝る義時軍が圧勝し、和田一族は力尽き和田義盛は敗死した。
この合戦の勝利により、執権体制を強固なものにした。
北条義時はあくまでも将軍を補佐する執権するポジションにいて、「執権」=「政所と侍所のトップに立つ最強の役職」となったため、逆らえるものが幕府内にいなくなった。
北条時政は執権職を完全なる北条氏の世襲制にしていき、次代を阿波局との子北条泰時(この時29歳か30歳)が継がせていでます。
北条義時と尼将軍の承久の乱
建保6年(1216年)1月27日実朝は右大臣就任を祝う為鶴岡八幡宮を参拝、その帰路に頼家の子公暁に襲われ落命する。
承久元年(1219年)2月13日、政子は後鳥羽上皇に六条宮(雅成親王)と冷泉宮(頼仁親王)のどちかを将軍として迎えたいと上申した。
同年3月9日に後鳥羽上皇が義時に対して、摂津国の長江荘と倉橋荘の地頭職を廃止するよう勅命を下したが、上皇の申し入れと親王将軍の申し入れと共に交渉決裂した。
『吾妻鏡』の記事によると、後鳥羽上皇の二度にわたる地頭廃止の宣旨を下したが、義時は幕府の根幹揺るがすとして拒否したため上皇の怒りりは凄まじかったという。
政子と義時は、親王将軍を諦めて摂家将軍を迎えることにした。
同年7月19日、左大臣九条道家の子三寅(2歳:のちの四代将軍・藤原頼経)が鎌倉に下向(頼家は源頼朝の姉妹・坊門姫の曾孫)。
※上記の藤原頼経をクリックすると関連記事があります、興味ある方は読んでください。
よって後見役となった政子は「尼将軍」と呼ばれるようになっていった。
承久3年(1221年)5月15日に後鳥羽上皇が、北条義時の追討の院宣を発する。
日本の歴史上天皇の宣旨に歯向かって勝者となった者は一人もいません(例えば、平将門の乱や平治の乱や奥州合戦など)などで、後鳥羽上皇の挙兵に多くの御家人たちが動揺した。
御家人たちの動揺をいち早く察知してのは、他ならず政子でした。
源頼朝の妻として御家人たちの目の前で名演説を行い、御家人たちの心を繋ぎ止めた。
※上記の演説をクリックして貰うと、北条政子の演説のセリフの記事があります、興味ある方は読んでください。
北条義時を総大将として京に攻め込み、後鳥羽上皇軍を討ち勝利した。
これによて武士政権が確立した。