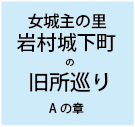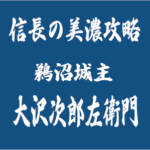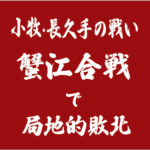こんにちは、当ブログの管理人です。
当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。
ごゆっくりご覧なってください。
岩村町の岩村醸造で、「女城主」新酒の蔵開きが、2025年2月8日・9日(これは終わりました)・22日・23日・3月1日・2日に行われています。
岩村町本町通りある、岩村醸造(株)の「蔵開き」についての案内をしたいと思います。
岩村醸造が開催するもので、美味しいお酒の試飲です。
是非来て試飲して自前・お土産に買ってください。
地元の文化・歴史を楽しむことができる素晴らしい機会です。
岩村醸造は、江戸時代の天明7年1787 年創業で、大正10年、岩村町で2番目となる株式法人設立と同時に、日本酒の他に味噌、醤油造りもはじめました。
岩村町に岩村城が出来たのが古く、約830年前に鎌倉時代に源頼朝の重臣・加藤景廉がこの地方の地頭・守護を任されたのが始まりです。
※.上記の加藤景廉をクリックして貰うと詳しい説明が書いてあります。興味のある方は読んでください。
現・城下町の位置は、天正時代に信長が武田軍の秋山信繁・おつやの方と戦って岩村城を奪還して城を織田方にして、その時の城主・河尻秀隆が富田地区にあった城下町を移転して岩村川から水を引いて各家庭の裏庭に天正疏水を通しまちた。
※.上記の秋山虎繁とおつやの方の記事がそれぞれ詳しく書いてあります。興味ある方は読んでください。
※.上記の河尻秀隆をクリックして頂くと城下町移転の記事が書いてあります。興味ある方は読んでください。
 ▲天正疏水
▲天正疏水
皆さんが試飲に行く岩村醸造にも天正疏水があると思います。
スポンサーリンク
蔵開きのイベントの概要
イベントの情報から紹介します。
日程:2025年2月8日(土)・9日(日)・22日(土)・23日(日)・24日(祝)・3月1日(土)・2日(日)
開催時間: 10:00〜15:00
会場: 岩村醸造株式会社
住所:岐阜県恵那市岩村町342
お問合せ:(0573)43-2029
交通:明知鉄道「岩村」駅より約歩15〜20分
中央線・明知線で来る場合「恵那」駅で下車して乗り換え
明知線の「恵那」発→「明智」行きは大体1時間に一本しか運行していません。
「明知線全駅名を表示」
恵那(始発)・東野・飯沼・阿木・飯羽間・極楽・岩村・花白温泉・山岡・野志・明智(終点)
「時刻表」を表示。
「恵那」駅発→「岩村」駅着→「明智」駅行きです。
AM : 6:46・8:04・9:17・10:18・11:20・12:25(急行)・13.:3・15:14・16:38・17:56・19:08・20:25・21:46 (最終です。)
帰りは「岩村」駅発→[恵那」駅着、昼からを記載します、
PM :12:55・14:14・15:44・17:09・18:27・19:39・20:56分(最終です、)
この時刻表は2024年3月16日の時刻表です。
ここに名古屋方面から岩村までのアクセスを書いたブログを載せます。よかったらみてください。
※.上記のアクセスをクリックして頂くと案内ブログがあります。
スポンサーリンク
岩村醸造の歴史
<岩村醸造は、岐阜県恵那市岩村町にある酒蔵で、天明7年(1787年)創業、もともと蔵元に渡会家が岩村藩に年貢として納めてた米を活用して酒造りを始めたことが起源です。
大正10年(1921年)には、岩村町で2番目の株式法人として正式に設立され、当初は味噌・醤油の製造をしていましたが、やめて酒造業に専念、そのため岩村醸造の社名に「酒造」ではなく「醸造」の二文字を使っています。
当会社は、地元の米と約400年前に掘られた井戸水を使用し、伝統的な手作業による酒造りを続けました。
はじめは「えゑなの誉」今では代表的な「女城主」がありネーミングは遠山氏最後の城主・遠山景任の妻(信長の年下の叔母・おつやの方)に跡取りが出来なくて信長の4男を養子に貰い岩村城を治めていたが、武田信玄の西上作戦のため重臣・秋山虎繁に攻められ開城します。
そこから付けたネーミングだと思います。
なかなかヒットしたネーミングだと思います。
そのときに先頭に立って戦ったといわれていて女城主といわれた。
ここに岩村城の歴史の事を書たブログを載せておきます。
スポンサーリンク
岩村町は歴史の町です。
岩村城の始まりは、加藤景廉が鎌倉時代に地頭・守護を任じられ嫡男・加藤景朝が築城(名前を遠山景朝にする)それから何代続いたか不明です。
遠山氏最後の城主・加藤景任(妻は信長の叔母・おつやの方・俗に女城主)・武田方・織田方・豊臣方・徳川方の城になっていきます。
ざっと話をしますと、承久の乱の時、鎌倉幕府が敵後鳥羽天皇と戦い、その公家の重要人物、一条信能を京都で捕縛し鎌倉へ輸送する途中で、今の神社がある場所で処刑し村人が信能を哀れんで葬った場所が相原の岩邨神社として祀ってあります。
明治13年(1880年)6月28日、明治天皇が中山道御巡幸の折、岩村へ勅使を派遣され祭祀料を賜った。
中心部の枡形地形の場所に祥雲寺(庚申堂)があり三基石仏狩ますが地元の最古の石像物、ここで八日恵比寿が開催されます。
一色には石室千体仏があり、上町には八幡神社・一色には武並神社、殿町には信長の嫡男・織田信忠が岩村合戦の時陣を貼った大将陣公演・日出町には丹羽氏の影響にある妙法寺があります。
また、初代岩村城主・大給松平家乗が連れてきた殿町に盛巌寺・本町五に浅見家、勝川家、本町三に木村家・浄光寺(ここからは住職の娘が大奥の老女・桃光院の実家)、明治天皇の妻・美子に可愛がられた、実践女学校の創設者・下田歌子、桜の花の第一人者・三好学、佐藤一斎、林述斎、遠山の近さん、鳥居耀蔵などのURLがあります。
※.上記の浄光寺をクリックして頂くと浄光寺の娘さんが大奥の老女になった記事があります。興味ある方は読んでください。
岩村城最後の城主・松平乗任に名古屋城尾張藩62万石の釣姫が輿入れした。
釣姫は徳川幕府の第11代将軍・徳川家斉の孫娘、父は名古屋城主・徳川斉荘が駕籠の漆でかぶれて病死した悲しい物語が伝えられています。
今も岩村町大通寺の隆崇院に立派なお墓があります。
※.上記の釣姫をクリックして頂くと詳しい記事があります。興味ある方は読んでください。
それぞれの記事は、一まとめにしたリンクを貼っておきますから、興味ある方はクリックして読んでください。
※上記の一まとめをクリックして頂くと岩村の歴史の記事が多く載ってます。興味ある方はご覧になってください。
食べ物
岩村名物・かんから餅を食べていくかお土産に持って帰ってください。
伊勢の赤福より美味しいと思います。
※.上記のかんから餅をクリックして貰うと記事が出てきます。興味ある方はご覧になってください。
もう一軒岩村名物がありましたが、ご主人が亡くなり今は細々と営業してる程度ですので味噌漬け牛蒡・唐芋の漬物。その他がありますが現在は分かりません。
店の名前は水半漬物販売店です。
見どころ
木村家の裏に浄光寺があります。
11代徳川将軍・12代将軍の時代に大奥の老女・桃光院を務めたお寺があります。
岩村城主2代が造った石室千体仏があります。
山岡町には飯高観音があります。